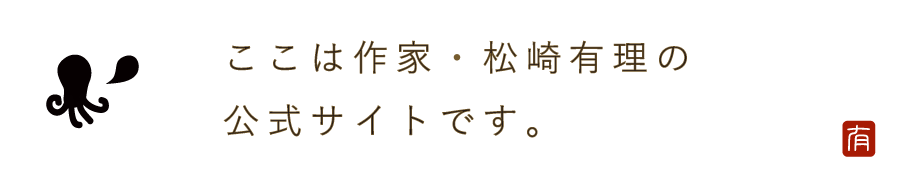作成日:2017/09/11 最終更新日:2017/09/18 かいたひと:松崎有理
そのあんぱんをひとくちかじってぼくは驚愕した。
あわててのこりを二分割し、右手に持った片方を目の高さより上にもちあげてみる。割った部分からのぞく小豆餡は、晩秋の午後の淡い日差しに透けてうすいむらさき色にみえた。
はんぶんになったあんぱんをみつめて黙考する。究極、ということばがふと思い浮かんだ。究極の問い、究極の解法、そして究極の答え。究極の芸術品や究極の酒、究極の料理なんてものもあるだろう。
もしもあんぱんの世界に究極が存在するのなら。
鼓通と喜多六番丁通が交差する地点、農学部敷地の一隅に食いこむように建っている古い神社を振り返る。かえでの巨木の下にたたずむ小さな社の前には、さいごの一個となったあんぱんがさきほどまで入っていた籐かごと、上面に細い穴のあいた木製の料金箱がならべて置かれていた。この組み合わせがだいぶ前から蛸足大学学内のあちこちでみられることには気づいていたが、買ってみるのははじめてだった。
いまぼくが昼食がわりに白銅貨一枚で手に入れたのは、あんぱんの究極なのかもしれない。
そばにとめていた相棒の自転車、彗星号によりかかって、こぶし大ほどのこぶりなあんぱんのはんぶんを口に押しこむ。餡の甘さと生地の甘さがじんわり口内にしみわたった。その瞬間、きょう午前中の学内営業がうまくいかなかったことも先日しあげた代筆論文が目標の学術雑誌から掲載拒否されたことも忘れ去った。
うまい食べ物はひとを真にしあわせなきぶんにする。これはやっぱり、あんぱん世界の究極なんだ。
残ったはんぶんを食べようと口をひらいたとき、目の前の喜多六番丁通を西方向から軽自動車が一台走ってきた。箱形で黄色い塗装のその車はぼくと彗星号の前で横腹をみせてとまった。側面には赤い丸文字で大きくこう書かれていた。
無人販売 あんぱんラパン
運転席側、つまりぼくからみて車体の反対側の扉がひらく。だれかが降りる。自動車の鼻先を回ってこちらに近づいてくる。
あんぱんを手にして口をあけたまま、そのひとをみつめた。
敷地の奥にある実験農場から、べえええええ、とかすかに羊の鳴く声がする。
「あら。うちのあんぱん買ってくださったんですね」
少し年上にみえるその女性はほほえんで、はっきりした二重まぶたの大きな目でぼくをみつめた。古典的な踊り手みたいに髪をうしろでひとつにまとめて、食べ物をあつかうひとらしい清潔感をかもしだしている。近くでみると、彼女はぼくよりずいぶん小柄だとわかった。だが頭は小さく手足は細く長く、均整がとれている。ほんとに踊りのひとみたいだ。
あんぱんラパンの経営者はみえない線のうえを歩くようにまっすぐ神社の前までやってきて、空の籐かごに料金箱を入れていっしょにかかえあげ、こちらをふりかえった。
「お口に合いましたでしょうか」首をかたむける。厚手のはおりものからのぞく首筋が優雅な曲線を描く。
とてもおいしいです、と月並みな答えを返し、のこりはんぶんを口に押しこんだ。だが口のなかはひどく乾いている。味どころか感触すらわからない。
よかった、と彼女はまた微笑する。「今後もごひいきにおねがいしますね」
苦労しいしいあんぱんをのみこんでから、はい、という。
晩秋の風は冷たいのに、手のひらと額に熱い汗がにじむ。わずかに残ったかえでの枯れ葉が枝から落ちて、ふたりのあいだを通りすぎる。
べえええええ。また羊が鳴いた。
究極はやっぱり存在するんだ、この世界にも。
***
十一月にはいるともう、北の街はりっぱな冬だ。
夜が長くなり気温がさがっていくにつれ、ぼくの睡眠は少しずつ深く長くなる。眠っている時間が夏にもましていとおしくなる。人間も冬眠したっていいじゃないか、とくにこんな寒い地方では。
だが現実にはそうもいかない。
「はい」受話器をとって、鳴りつづける電話をだまらせた。頭の一部にはしあわせな夢のつづきがまだ残っていて、体のまわりを備蓄食料のどんぐりと枯れ葉のふとんが丸く囲むように埋めていた。枕はじぶんのふさふさしたしっぽだ。
つまりぼくはさっきまで冬眠中のしまりすだった。
「起きたか」電話の相手はやはりトキトーさんだった。「というか。寝てたな、いままで」
はい冬眠してました、とはいえない。「すみません。ゆうべ遅かったので」枯れ葉、ではなくふとんから這い出して電話の前の床に正座する。
「べつにあやまることじゃない」彼は電話口で豪快に笑った。耳が痛くなるような音量だ。おかげでしまりすだったぼくはかんぜんに人間にもどった。どんぐりも枯れ葉もふさふさのしっぽもみえなくなった。「おまえもりっぱな自営業者だ、時間はじぶんで律すればいい」
はい、と答えて室内をみわたす。学生時代から通算五年近くもすんでいる八萬町の古い部屋には、だいぶ高くなった太陽の光が南側の大きな窓からさしこんでいた。床の日だまりに、だいじなともだちであるさぼてんの小さな鉢が鎮座している。日々の気温はさがってきたが、彼女はきょうも元気そうだ。
「ところで本題だ。よろこべミクラ」先輩代書屋の深く大きな声はつづく。「依頼を一件、回してやる」
心から礼をいう。代書屋となって半年、仕事をとってくるむずかしさを実感しつつあった。営業とは九割がた失敗するものだ。研究者をひとりひとりあたっても、けっこうです、論文はじぶんで書けますから、といわれてあっさり追い返される。研究者にかぎらず人間は一般に、押し売りされるのがきらいなのだろう。さいきんになってようやく、そう気づいた。
だからこうして、トキトーさんが仕事を振ってくれるのはものすごくうれしい。
だが。彼から紹介される依頼には、最低ひとつのむずかしい問題がからんでいる。
「ええと。どちらからでしょう」トキトーさんはじぶんでやりたくないからぼくに回してきたのだろう。彼自身は仕事に困っていない。
「農学部だ」
脳内の、さきほどまで枯れ葉とどんぐりが覆っていた位置に、天宮地区にある農学部の風景が浮かびあがった。医学部近くの一等地にもかかわらず広大な敷地、そこをかこんでいるつたの這った煉瓦塀、年季の入った石の門とそのそばの小さい山小屋みたいな守衛詰所。なかの建物群は開学当初から建て替えられておらず、老朽化いちじるしいが味わいがある。実験農場では学生たちがいちごや野菜の手入れをし、みつばちを飼い、羊の群れの世話をする。
ふるくてのんびり。それが農学部の雰囲気だ。
先月、あんぱん販売店主にはじめて出会ったのも、この場所だった。
「依頼人の専門は農業経済学、肩書きは准教授。きょうの午後いちで打ち合わせしたいそうだ。行けるか。行けるな。行け」
枕元の筆記具をとりあげ、依頼人の名前と研究室の電話番号を書きとめる。さいごにもういちど礼をいって通話を切った。
アカラさまにも感謝の祈りをささげた。また仕事がきました。ありがとうございます。
金泥で隈取りされた赤い面をつけたぼくだけの神は、羊の群れのむこうで長い前髪をゆらしながらなんどもうなずいていた。
よし、唄もささげようか。
文学者と経済学者と数学者が
いっしょに旅行にでかけたよ
「ごらん」文学者が車窓を指す
「この地方には黒い羊がいる」
「ちがう」と、経済学者
「正しくは。この地方には少なくとも一頭の黒い羊がいる、だ」
「そうじゃない」数学者は首をふる
「この地方には、体のこちらがわが黒い羊が少なくとも一頭いる、が正しい」
アカラさまは羊のもこもこした背の上でたのしげにゆれている。この神は唄がだいすき、という設定だ。なおぼくの頭のなかにいるのは幻影みたいな仮の姿で、本体は遠い南の島にすんでいる。
脳内風景でひとしきりアカラさまと遊んでから、現実の自室にもどって壁掛け時計をみあげた。もうじき昼だ。農学部の学食でゆっくりと名物の羊からあげ定食を味わっている余裕はないらしい。
じゃあ。またあんぱん買おうかな、もしまだ残っていたら。
農業経済学研究室はびっくりするくらい活気づいていた。
指定時間の五分前に農学研究棟にたどりつき、教えられた番号の扉をたたいて入室すると、ふるくてのんびり、という学部全体の印象とはまるでちがった光景が目に飛びこんできた。
ふた部屋ぶち抜きの広い室内には、十数人ぶんの平机と背の高い本棚がおさまっている。学生や大学院生は数人ずつ固まって討論するか、若手教官をつかまえて熱心に質問している。その間を秘書とおぼしき若い女性や、ぼくとおなじような黒服を着た業者たちがせわしげに歩いていた。ぼくが口をあけてながめているうちにも、べつの業者がごめんなさい、といいつつ大きな箱をかかえて入ってくる。
研究室出入口よりの一角、来客用の長椅子と卓と丸椅子の奥に、ひときわりっぱな書き物机がすえられていた。三十代後半にさしかかったばかりとみえる浅黒い肌の男が立ちあがり、手招きしてくる。固そうな髪は四角く刈りこまれ、あごはいかつくふたつに割れていた。縦縞柄の上衣をきた肩幅はずいぶん広い。
このひとが依頼人だな。
業者や学生を避けつつ彼の前まで進み、一礼する。「代書屋です。ミクラといいます。このたびはご依頼ありがとうございます」
相手は冷静な表情で書き物机ごしに礼を返し、腕時計をみた。「三分前。合格」
試験されていたのか。