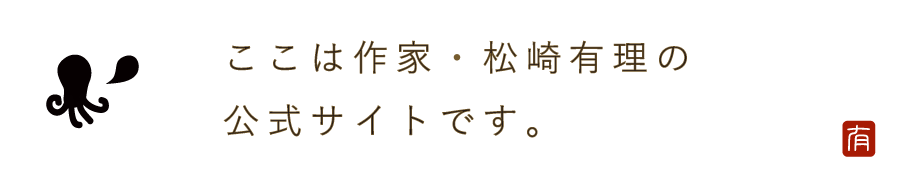作成日:2017/09/11 最終更新日:2017/09/19 かいたひと:松崎有理
ことわってもことわってもゆでたまご 路傍土
路傍土というのは一行自由詩をつくるときのぼくの号で、この詩ができたのはとある喫茶店での衝撃的なできごとがきっかけだった。
いや、できごとというか、出会いだ。
小鳥踊りで有名な春祭りもおわり、北の街はゆっくりと初夏の陽気に変わりつつあった。その日はちょうど彗星号の誕生日にあたっていた。つまり、蛸足大学に入学したばかりのぼくがまいにちの講義のあと必死で時間給の仕事をして、ためたお金で新品の自転車を買った日だ。だからふだんより少しだけ早く起き、めでたく六歳になったこの相棒とともに研究地区へ営業に出かけた。
そのとちゅう。
けやきの若葉のあいだから光がふりそそぐ上善寺通の歩道に、まあたらしい脚つきの立看板をみつけた。黒板を模した腰ほどの高さの看板上部には白い文字でこう書かれていた。
あなたの居間 喫茶店メリメ
いい惹句だな。あなたの、と二人称で語りかけているところがいいのかも。それともほんのり古くさいところか。
営業の前にのぞいてみよう、どうせ時間をきめた約束があるわけでなし。
歩道のすみに彗星号をよせ、鎖で鍵をかける。お二階へどうぞ、という看板の矢印にしたがって無骨な鈍色の建物に入り階段をあがった。
せまくて暗くてきゅうな階段をのぼりきってすぐ、喫茶店メリメと書かれた木製扉があった。
取っ手を引く。からからん、と鈴の音がした。なんとも古くさい演出だ。子どものころ、故郷の町にはこんなかんじの店がいくつもあったっけ。
店内は明るかった。上善寺通側に大きな窓がならんでいるせいだ。広めの卓がいつつほど、椅子はすべて肘掛けと背もたれつきで、この種の飲食店につきものの長い卓と小さな高い椅子からなる一人席はみあたらない。壁ぎわには書棚があって雑誌と新聞がたくさん入っている。書棚のうえには花瓶が置かれ、ひとかかえぶんもある桃色の花が活けられていた。数人いる客はみな引退した年齢の男性で、珈琲の杯を前にたばこをくゆらし新聞をよんでいる。自宅にいるかのようなくつろぎようだった。
うん、たしかに居間だ。
空いた卓のひとつに歩みより、布張りの椅子のやわらかい座面にふかぶかと尻を埋めた。うんうん、こいつはたしかに居間っぽい。
「いらっしゃいませ」
卓上の品目表をながめていると頭上から声が降ってきた。
顔をあげる。腰をしぼった純白の前掛けが目に入る。ぼくの両手で囲えるんじゃないかと思うくらい細い腰だ。だがそのうえにはすばらしく豊かな胸部が乗っていて、釦をふたつあけた黒の上衣のあいだからは光る石の首飾りがみえた。
「ご注文は」彼女はそういいながら、爪をみじかく切りそろえた清潔そうな白い手でぼくの前に水のはいった硝子の杯を置く。それから湯気のたつおしぼりを手わたしてきた。
喫茶店で、紙製の使い捨てでない、あたたかい布のおしぼりを出されるってものすごくひさしぶりだ。
「ありがとう」おしぼりを受けとる。目があった。
純白の前掛けもかくやというほど色白の、あごの小さい、赤い口紅がよく映える、長い髪をひとつにまとめて木綿の頭巾で覆った、二重まぶたの両目がなんとも神秘的な、そしてたぶんずっと歳上の、美女だった。
「おきまりですか」彼女は笑みひとつみせずにそううながす。口調には耳慣れない抑揚がある。
よその土地からやってきて、ここに喫茶店を開いたのかな。
「あたたかい珈琲をひとつ」品目表のいちばん上を指す。はじめて入る喫茶店ではいつもこうしている、この位置に載っているのはその店の看板商品だからだ。
歳上の美女は手のひら大の伝票ばさみに注文を書きこみ、少々おまちください、といって店の奥へ去っていった。
うん、すばらしい。
彼女のうしろすがたを見送る。とてもよい絵画を鑑賞したあとのようなきぶんだ。椅子の背もたれに体をあずけて珈琲を待つ。
彼女がもどってきた。丸い盆から受け皿がついたおおぶりの陶器の碗をぼくの卓に移す。それからなにもいわずにごく自然に、小さな丸い皿を珈琲の横に置いた。
皿には殻つきのゆでたまごが載っていた。
「あの。これ、頼んでませんけど」
歳上の美女はやはり笑うでもなく、神秘的なまなざしでぼくをじっとみつめて口を開いた。
「おまけです。珈琲をご注文のお客さま全員に無料で提供しています」
この抑揚。やっぱりそうだ、よその地域のしゃべりかただ。
周囲を見回す。ほかの客の卓には、たしかに珈琲のほかに小皿があって、一個ぶんだか数個ぶんだかのたまごの殻が残っていた。
郷に入っては郷にしたがえ。そんな格言が頭をかすめた、しかし。
「でも、ぼく、いりません」小皿を彼女のほうへ押しやる。「さげてください。食べませんから」
だって珈琲とゆでたまごってよい組み合わせとはとても思えない。
驚くべき答えがかえってきた。「だめです」
「え」
「さげません。食べてください。おまけを断ったかたなんて、これまでひとりもいませんでした」彼女の口調は断固としており、目つきからはゆるぎない意志がかんじられた。美しさはすごみを増した。
「で、でも。やっぱりいりませんってば」いまこの時間、ゆでたまごを食べたくないのは事実だ。強制されればなおのこと食べる気は失せる。
だが彼女は一歩もひかない。「おまけですよ。どうです、おねうちでしょう」
おねうち。なんだ、聞き慣れない言い回しだ。「とにかく、いらないものはいらないんです。おねがいだからさげて」
白い手がさっと伸びた。皿のなかのゆでたまごをつかみ、振りあげて。
「あ痛っ」
ぼくの額で割った。
「どう。食べる気になった」
歳上の美女は片手を細い腰にあて、ひびのはいったゆでたまごを片手で突き出し、ぼくを見下ろしてふしぎな抑揚でそういった。
「はい」そう返事したころには、目の前の女性の神秘的なまなざしと赤くて小さい唇とすばらしくくびれた腰にすっかり心をうばわれているじぶんに気づいていた。
それで、先の詩ができたわけだ。
ぼくがとつぜん一行自由詩に凝りだしたのにはわけがある。
冬の帰省からもどってきて以来、心にぽっかり空洞ができたような気がしていた。
なにかがたりない。なにかが欠けている。なにかをどこかに置いてきてしまった感じがする。
しかしそれは失恋のせいだ、いや正確にははじまる前に失ってしまった恋のせいだと思っていた。だからきっと、新しい恋をすれば穴は埋まるのだと。
しかしそう都合よく恋に落ちるというのも期待はできないので、まずはこういうばあいの基本として仕事にうちこんだ。それに加え、新しい趣味をはじめようと考えた。ことばをつかうものがいいだろう、仕事に直結はしなくてもなにか役に立つかもしれないし。
でも、なんにしようかな。
思いあぐねていると、あるのっぴきならない用事で大家さん宅をおとずれたとき、玄関の掛軸にきっかけを発見したのだった。
掛軸にはひじょうな能筆でこんな詩が書かれていた。
さて、どちらへ行かう風が吹く
これまで一行自由詩というものにさして興味はなかったのだけれど、これをみた瞬間、やってみようときめてしまった。
だが思ったよりずいぶん早めに、恋に落ちる瞬間はおとずれた。かといってせっかくはじめた趣味をやめることもないだろう。
***
「お金がないんです」
そう訴えると、トキトーさんは隣の席からからだをかがめ、ぼくの顔をのぞきこんだ。そのまなざしだけは十年前の美青年だ。つまり、下あごやおなかまわりによぶんな肉がついてしまっている。
刻文丁通にある『オサリバンの店』はまだたいして客がはいっていない。地方いちの歓楽街であるこの界隈では、夕刻とは早朝みたいなものだからだ。勘定台前の長卓で高い丸椅子に座っているのはぼくとトキトーさんだけだった。
「いまにはじまったことじゃないだろ、そんなの」
そんなつめたい台詞をいって、先輩代書屋は琥珀に赤を流しこんだような色の麦酒をあおり、ああうまい、と息を吐く。ほんとうにしあわせそうな表情をする。
「いえ。今回の金欠はとくに深刻なんですよ」
麦酒の杯を置いて、事情の説明をする。
数か月前帰省した。けっこうな金額が交通費に消えた。しかも、その間うっかり家賃を滞納してしまい、大家さんを困らせたので滞納ぶんを一括でわたしたうえ、せめてものつぐないとしてその後三か月間の家賃を前払いした。さらにその際、おわびのしるしにじぶんとしてはずいぶん奮発した手みやげを持参した。そこでぼくのだいじな貯金はほぼ底をつく。
「なに持っていったんだ」
「ほや酢」
店内にしずかな空気が流れた。