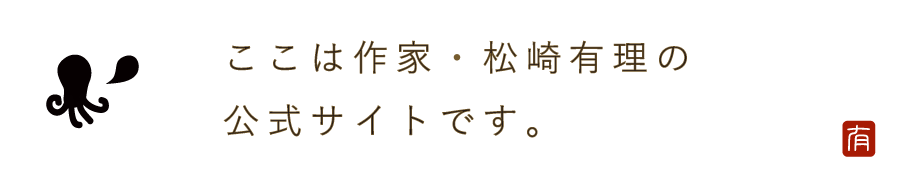作成日:2017/09/11 最終更新日:2017/09/17 かいたひと:松崎有理
特急に乗ったつもりがじつは急行だった、と気づいたのは、すでに旅程を半分もすぎたころだった。疲れのためか座席で熟睡していたので、じぶんの乗る列車がむやみにたくさんの駅で停車していることにまったく気づかなかった。
暖房で結露した窓を指先で拭き、外をのぞく。濡れた硝子ににじんでみえる冬の夜景は人家の明かりもまばらで、冴えた上空の星のほうがまぶしいくらいだ。
「まあ、いいや」膝のうえにかかえた円筒形の箱のふたをずらし、なかにいる小さなさぼてんの鉢に語りかける。「いまから特急に乗り換えたって到着時間はそんなに変わらないから。だいいちめんどうだし」
こうして自己説得すると、頭に載せていた麦わら帽子のつばを目のあたりまで引きおろし、ふたたびさぼてんの箱を抱いたまま眠りに落ちた。故郷の町は終点だ。
けっきょく、実家への到着は深夜になってしまった。
北の街を出るとき駅から母に電話を入れておいたけれど、早寝の習慣がある両親が起きているかどうかは心もとない。じっさい、ぼくの生まれ育った古い家は生け垣に抱かれて暗くひっそり寝静まっていた。だがいつものように、母は勝手口の鍵を開けておいてくれたようだ。
冷えきった取っ手を回し、扉を開けて、台所にあがる。名状しがたいなつかしい匂いがする。ほのあたたかい闇に包まれ、安堵の息を吐いた。
そのとき。
たたらったったーああん、と太鼓が鳴った。このあたりで聞かれる地味でにぶい音ではなく、南洋の民族楽器のように軽くて派手な響きだ。
ぼくはすっかり驚いて棒立ちになった。じぶんの実家なのに。
つづいて闇のなかから唄声がきこえてきた。よくとおる中低音の男声、節回しもあざやかでなかなかじょうずだ。
いのちみじかし恋せよ船乗り
板いちまいの下は海
三月ののちに彼女に会える
きっと港でまっている
握れ舵輪、睨め海図と六分儀
鴎のように風をよめ
嵐に耐えて凪をまて
おお、ひときれの雲もない大空の尊さ
水平線はいつでもまるい
唄がおわると台所の照明がついた。まぶしさに目を閉じ、ふたたび開くと。
赤ら顔の大男が立っていた。長くのばして編んだ前髪、それ以外にはいっさい頭髪がない。
あ。アカラさま。
「おかえり、ミクラ」大男はそういって、太い片腕でぼくの肩を音がするほど強くたたいた。どこかの民族衣装とおぼしき赤と黄色の貫頭衣を着て、腰には派手な緑色の鞘がついた太刀をおびている。「ひさしぶりだ。大きくなったな」もう片方の腕を突き出す。その手には巨大な酒びんがにぎられていた。
「のむか」笑っている丸い目だけは母とよく似ていた。
これがモーリオおじさんとの十八年ぶりの再会だった。
***
ここは北の街にくらべてずっと日差しが強い。真冬でも麦わら帽子があってちょうどいいくらいだ。
それもそのはず、この町はずいぶん南にあるし、だいいちここは海辺だ。しかもきょうは快晴、太陽はもうじき南中しようとしている。
そんなあたりまえのことをぼんやり脳内で反芻しつつ、海沿いを走る車線のない道路と砂浜との境界になっている段差に腰かけて、子どものころのように海をながめていた。あのときとちがうのはすっかり背が伸びて視点が高くなったことと、それから。
太陽の光が白く目を射る。あいたたたた、と声を漏らして額をおさえる。
麦わら帽子におさまっているこの頭が、ひどい二日酔いで痛むことだ。
うわばみもかくやというほど叔父は酒がつよかった。ぼくのほうは大学を出てから単価の高い麦酒専門、つまり量も度数もほどほどにたしなんできただけだ。いっぽう相手は流浪の船医、明日をも知れぬ身と飲みまくって鍛えたひとだ。はなから勝負にならない。
叔父は酒びんのはんぶんをぼくに飲ませ、のこりをじぶんで飲んだ。おおいに語り、おおいに笑った。ぼくはさいしょのうちこそ両親を起こすのではと気をもんだが、じき酩酊してどうでもよくなった。そもそも父も母もひじょうに寝つきのよいひとで、そんな心配など不要だった。
額に手をあてたまま考える。ええと、モーリオおじさんの話。どんなのだったっけ。
だが頭蓋骨のふちまで酒精につかった大脳は昨夜の記憶をつむぎだすことさえ難渋している。だから叔父の武勇伝は映画の予告編みたいな断片で浮かんでくる。
船が赤道を越えるとき安全を祈願しておこなう祭りの日、酔った叔父は仮装した船長を海の怪物と思いこんで船べりから放り出した。
鮫におそわれた乗組員を助けるため、大きく開いた鮫の口にすっぱい柑橘を五十個ほど投げこんで撃退した。
船員の疣痔の手術をすることになったのだが、おりあしく麻酔薬が切れていたので生理的食塩水を麻酔だと信じこませ、手術を決行した。
ほんとうなのか、ほらなのか。
こめかみの部分を指でさすり、むりに細部を思い浮かべようとすると、赤い面をつけた脳内神のアカラさまが出現した。叔父と似た長い前髪を振り動かしながら熱帯の海辺をじゃぶじゃぶと泳いでいる。やたらたのしげなのは海水がすべて酒だからだ、とじきに気づいた。
ああ酒はいとしい悪魔かにくらしい天使か。
と、叔父がうたっていたことだけは思いだせたので、その唄をそのままアカラさまにささげた。
かといってこの神が頭痛を解消してくれるわけではない。ただぼくの脳内にいて、見守るだけの神だから。
でん。でこでこでこでこでででこでこでこ。でんでん。低い響きが大地を伝わり、ぼくの腰から這いあがって、過敏になった脳を刺激する。
祭りの練習だ、と痛む頭のすみで思う。発作的な帰省だったけれど、おりよく冬祭りの直前に帰ってこられたな。
あの祭りをみるのも何年ぶりだろう。子どものころはよく行ったけど、成長するにつれ地元の祭りからは遠ざかっていったっけ。
祭りの夜か。
記憶は昨夜を通り越して一気に十数年をさかのぼる。
篝火の明かりに照らされた幼いぼくの手はひどく小さく、ぼくの手をにぎっている白い手もやはり小さい。周囲の闇はねっとりとした甘い匂いに満たされている。背景では低い太鼓の音がつづいている。この音と匂いは町の冬祭りに特有のものだ。
とにかく、ぼくたちは手をにぎりあっている。揺れる炎が映るおたがいの目をのぞきこみ、どちらからともなく誓いのことばをいう。
おおきくなったらけっこんしようね。
刺すような痛みが片方のこめかみからもういっぽうへつきぬけた。頭をかかえ、顔を膝にふせる。ああ、あのころのぼくはこの二十三年の生涯でいちばん幸福だったのかもしれない。
アカラさま。ぼくのしあわせはもどってこないのでしょうか。
じぶんだけの神にそう訴えた直後、だれかに声をかけられた。
「あれ。ひょっとしてミクラ」
帽子のつばを払い、顔をあげる。過去の幸福への喪失感と二日酔いでにごった目をしているであろうことは自覚していた。
「やっぱりそうだ」と、その声はつづく。
しかしぼくのほうからは逆光で、相手の姿がみえにくい。数回まばたきして目を慣らす。
数歩先の砂浜で、小柄な丸顔の女性がほほえんでいた。
焦点を合わせようとまたまばたきする。そのたびに、これまで好きになった女性たちの姿が二重写しになる。
「やだな、おぼえてないの」
あかるい色の髪は肩のところで先が巻いている。みじかい外套の袖から小さな手がのぞいている。その白い手をあげ、軽く振った。
なにもいえずに相手をただみつめる。
「こっちはすぐにわかったよ。だって真冬に夏の帽子かぶってるのなんてミクラしかいないもの」彼女は手を振りながらくすくす笑いつづける。「変わってないね、ほんと」その小さな白い手は、約束をしたときの、あの手だ。
思いだした。
「イッチャン」ぼくは帽子をはねあげた。「こっちに帰ってたんだ」
「まあね」十八年ぶりに再会した幼なじみは、両手を腰のうしろに組んでこちらに笑いかけてきた。
二日酔いに負けずせいいっぱいの微笑を返す。アカラさまありがとう。過去の幸福がいま、戻ってきたようです。
頭のなかの神は、酒の海で顔と腹だけを出してたゆたっている。
***
「さっそくイッチャンに会ったんだ。よかったねえ」
南向きの大きな硝子戸から午後の日差しがさしこむ居間で、母はのんびり編み棒をあやつっている。
ぼくは床に広がる陽だまりのなかに猫よろしく寝そべって丸くなり、母の手つきをながめている。そばには北の街からはるばる連れてきたさぼてんの鉢がある。さぼてんとぼくはそろって日光を受け、ごきげんにあたたまっている。
「引っ越しの日、おぼえてる。おまえったらおんおん泣いて」
「やだな、へんなこと思いださないでよ。五歳のころの話じゃない」
えんぴつみたいにとがった編み棒の先が毛糸を巻きとり、もう一本の棒にできつつある編み物本体のいちばん端の目を通って、またもどる。すると編み目がひとつ増える。この作業をたんたんと繰り返す。
母の動きはよくいえばていねい、悪くいえば異常に遅い。手袋になるのか襟巻きになるのか上衣になるのか、いまだまったくわからない。ひょっとしたら鍋敷きかもしれない。おまけに複数の作業を同時に進めるのがすきだ。
母はその弟とは対照的に小柄で、足を投げ出して座っている緑色の長椅子ははんぶんほども空いている。その空いた場所につくりかけの編み物が編み棒を刺したまま色とりどりにみっつもよっつも散らばっていた。
これ完成するの、夏になるころだろうな。どうせまた。
「ところでイッチャンこっちにいつ帰ってきたの」浜辺で長く話す時間はなかった。ぼく自身の近況を少し語ったところで、休憩がおわるから、と彼女は立ち去ってしまった。
「ええとね。三年前かな」母は手をとめて天井の梁をみあげる。小さな町だ、この種の情報は容易に伝わる。「中央の大学を中退してきたんだって」
え。中退。
「よっぽどやりたかったんだろうね、あの仕事」母はぼくの驚きなどまったく気にとめないようすで編み物を再開し、小声で唄までうたいだした。
恋愛とは おたがいをみつめること
結婚とは おなじ方向をみつめること。
母の唄をききながら体を返して仰向けになり、両腕を頭の下に組んで天井をみつめる。
イッチャンの仕事については去りぎわにちょっとだけきいた。たしかにおもしろそうだし、やりがいもあるだろう。
だが、大学を辞めてまですることだろうか。