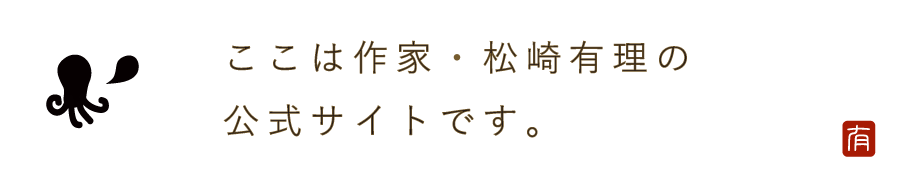作成日:2017/09/03 最終更新日:2017/09/15 かいたひと:松崎有理
「名前を教えてください」
刻文丁通の花屋を三度めにおとずれた夜、店員の彼女に思いきってそうきいてみた。
彼女はぼくが買った一本きりの赤いばらを包む手をとめて、目をあげた。白い丸顔が微笑する。小さな唇が動く。
「レニエです」
それはこの店の名前だ。
だがぼくはそんなつっこみもできないほどの衝撃をおぼえていた。こんなに不思議な受け答えをする女の子は大学にいない。そう、なんというか、彼女は。
超現実だ。
社会人になるってこういうことかもしれない。花の代金をわたすぼくの手はかすかにふるえていた。
ありがとうございました、という彼女の声をききつつ、花屋を出た。両肩にかけた背嚢型の黒いかばんを揺すりあげ、店の前にとめていた相棒の自転車、彗星号に乗る。
薄紙に包まれた花を片手に、せまい歩道からあふれる酔客や客引きを避けながら刻文丁通をゆっくり走った。この界隈はこれからがほんらいの活動時間帯だ。飲食店のまぶしい明かりが、派手な色と大きな活字の看板が、出勤とちゅうの玄人女性たちの高く結いあげた髪やあざやかな衣装が、ぼくと彗星号の左右をかすめていく。
春の夜風は上下そろいの営業用の黒い服を平気でつき抜け、体を凍えさせようとする。北の街では、春といっても冬の延長のようなものだから油断ならない。
しかしぼくは、そんな伏兵みたいな春先の寒さなどまるで気にしてはいなかった。
***
「よろこべ、ミクラ」電話の声は大きく、よく響く中低音で、相手がトキトーさんだということは寝起きのぼくでもすぐにわかった。「依頼を一件、回してやる。おまえの初仕事だぞ」
「あにまとうございます」まともに口が動かない。朝っていつもこうだ。
この春からぼくを代書屋稼業にひきこんだ男は、依頼人との顔合わせは今日の昼からであることをまず告げた。「相手は、工学部応用心理工学研究室の助教だ。行けるか。行けるな。行け」
仕事、初仕事だ。
ぼくのからだと思考はようやく働きだした。
「ちょっと待ってください」布団から出て床に座り、電話のそばをさぐって筆記具をとる。「なんですか、応用心理工学って。きいたことないですけど」
「そりゃそうだろう」彼はさらりと返した。「今年度から新設されたんだ。だが工学部の敷地案内図にはちゃんと載ってる。もしわからなかったら、かけろ」と、数字をならべたてる。
研究室の直通番号か。
ぼくの内部でじわじわと緊張が高まってきた。「ちょ、ちょちょちょっと待ってください」
「なんだ」相手のほうは、いつものように自信ありげで落ちついた声だ。
「ぼ、ぼぼ、ぼぼぼぼくひとりですか、いきなり。は、ははは初仕事なのに」
「なにか問題でも」先輩代書屋の微笑が目に浮かぶようだ。「おれは別件をかかえていて忙しい。だからおまえに回したんだぞ。それに、この日にそなえて訓練はやっただろう、それなりに」
「はあ」たしかに、それなりには。
相手はうんうん、と満足そうに返してきた。「だいじょうぶ、教えたとおりに動け。むこうだって人間だ、臆することはない。それにおまえ、研究者がどんな連中かってのはわかってるだろう、それなりに」
「はあ」もちろん、それなりには。
トキトーさんは依頼人の所属と連絡先をくりかえしてくれた。
書きとった内容を復唱し、先輩代書屋にもういちど礼を述べて、通話を切った。
ほんとにだいじょうぶかなあ。
ぺったり床に座ったまま、応用心理工学、と書いた自筆の文字をながめる。工学なのか文学なのかよくわからない、こんな分野名もめずらしくなくなった。さいきん、あらゆる大学は学部学科や研究科を統合したり新設したり名前を変えたりすることにやたら熱心だからだ。
トキトーさんとぼくが卒業し、営業範囲としているこの歴史ある蛸足型の総合大学だって、例外ではない。
以前、おなじ理学部の友人がこぼしていたのを思い出す。おれはねえ、地質学科に進学したつもりだったんだ。ところがおれが入ったその年から、全地球惑星圏環境共生科学科とかいう、なにをするところか見当もつかない名前になっちゃって。あれにはまいったね。
科学史科は、科学史科のまんまだったな。運がよかった。まあ、名前を変えたくらいで劇的ににぎわうようになるとも思えないけど。
学生時代から住んでいる八萬町の古い部屋をながめわたした。南むきの広い窓から朝の光がふんだんに差しこみ、食卓の上の一輪挿しと、昨夜買った赤いばらの花を照らしている。窓に覆いをしなければ朝日のせいで早起きできる、というのは迷信だ。すくなくともぼくにとっては。
立ちあがって食卓にかがみ、ばらに話しかける。「おはよう、レニエさん」
もちろん花は返事などしない。
わかってる。しゃべらない花にあいさつするのも、そして恋愛も、ひとりよがりの自己満足だ。この事実は二十三年も生きれば身にしみて理解できるようになる。
一間きりの居室につづくせまい台所に立つ。湯をわかすあいだ、じぶんでつくり出した神であるアカラさまに感謝の祈りをささげた。
ありがとうございますアカラさま、あなたのおかげです。
トキトーさんは当初の約束どおりに仕事を回してくれました。しかも、資金が潤沢といわれる工学部からの依頼です。とぼしくなった貯金も回復できるでしょう。
貯金か。
花屋店員の姿が浮かぶ。頬がゆるむのがわかる。
アカラさま。いいころあいで、仕事がきましたよ。
金泥で隈取りされた赤い面をかぶり、長い前髪をたらした姿のアカラさまは、ぼくの頭のなかでなんども大きくうなずいた。なにごとも順調なとき、よくみせるしぐさだ。
この神は、ぼくが四歳のとき水とお湯の蛇口をまちがえてやけどした瞬間、脳内に降臨した。さいしょはぼんやりした影みたいなものだったが、以後さまざまな設定を加えながら信仰してきた。前髪は長いけど後頭部はつるつる、とか、本体は遠い南の島に住んでいる、とかだ。その結果、いまではすっかり真にせまった脳内神となった。これらの設定はあまりに増えすぎたため、ぼくですら忘れることがある。
手動の豆挽き器で珈琲豆を粉にし、濾紙にのせる。湯をそそぎ、珈琲を落とす。趣味か風流と思われそうだがじつは節約のためだ。料理でもなんでも、うまく安く、を追求すると自作するのが最善とわかる。
こうして淹れた珈琲を飲みおわるころには、朝に弱いぼくの頭とからだもさすがに目覚めてくる。
応用心理工学科の助教、ぼくのはじめての依頼人は、三十歳くらいのさもかしこそうな男前だった。
袖口に糊をきかせた皺ひとつない無地の上衣を着ている。短く刈った髪ときれいにあたったあごは洗いたてみたいな印象だ。表情まで洗い落としたみたいだ、白い頬にはかすかな笑みすらない。
こっちは必死で営業用の微笑をつくってるのに。
依頼人は書き物机から書類の束をとりあげ、回転椅子をまわしてこちらをむくと。
「今回きみにやってほしいのは、これだ」と、差し出してきた。
さあ、仕事、仕事だぞ。ぼくはもう学生じゃない。
椅子をすすめてもらえないので立ったまま書類を受けとり、さいしょの頁をながめる。
研究主題らしき一文が大書されていた。
『結婚と業績の相関 男性の研究者や芸術家は結婚後に生産性が落ちる』
いけすかない内容。