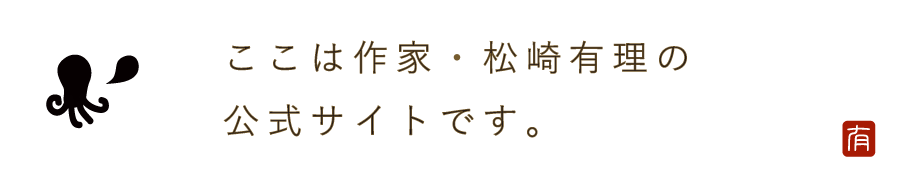作成日:2017/09/02 最終更新日:2017/09/02 かいたひと:松崎有理
ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしいことだと思われた。 寺田寅彦「小爆発二件」
***
少年が敵の姿をはっきり認識したのは五年生になったさいしょの日であった。
九月。まだまだ秋とは名ばかりの、強い日差しと亜熱帯的なスコールに悩まされる時期である。少年のクラスの担任となったのは新顔で、若く、きびきびした動きの小柄な女性だった。彼女は教壇に立ち、児童たちの前でファンと名乗った。きれいな発音の英語だった。四年のとき担任だったイギリス人男性教師よりもきれいなくらいだ。
「先生、かわいいっ」
「どのへんに住んでるんですか。旧市街、それとも新地区」
「スリーサイズは。好きなタイプは」
ませた男子たちがつぎつぎにませた質問を発する。女子たちは彼らを軽蔑の目でながめながらも、やはり若い新任教師にたいし興味津々だ。クラスの六割が中国系で三割がヨーロッパ系、残り一割がその他の民族集団で、少年はみっつめのカテゴリに属している。この街の公用語は歴史的経緯から南欧語だが事実上の共通語は中国語であり、観光都市という性格から学校での授業はすべて英語で行われていた。
「個人的な質問には答えられませんよ」ファン先生はベージュ色の丸顔をほころばせつつ教卓からクラスぜんたいをみつめる。目はアーモンド型で瞳の色は濃い褐色。肩の上でそろえたまっすぐな黒髪が開いた窓からの風を受けてさらりと流れる。丸襟の半袖シャツはまぶしいほどに白い。
「それじゃ」女子のひとりが手をあげた。「先生のいちばん好きな教科は、なんですか」透き通った肌と腰まで届くブロンド、緑色の両目、すっきり伸びた手足、と恵まれた容姿をもち、おおぜいの男子のほのかな憧憬を集めていた。少年も例外ではない。
「レオノールね」ファン先生はクラス一の美少女に笑顔を向ける。なんとこの新任教師は担当する児童たちの名前をおぼえてきたらしい。「よい質問です。先生のいちばん好きな教科は、これからはじまる一時間目の」
数学。
そのことばが少年の耳を貫き、ひどい頭痛を復活させた。新任教師をむかえる興奮ですっかり忘れていたのに、現実は少年を逃さなかった。
鈍器で殴られるような痛みに少年は思わず頭を抱える。周囲の景色も音も急速に消えて、いま彼の世界には痛みだけが存在する。
「くん。アキラくん」
彼の名前を繰りかえし呼んでいるのはファン先生だった。しかも、彼の母語で男子に使う敬称までつけて。「アキラくん。だいじょうぶ、顔が真っ青。保健室へ行きましょうか」
「先生、アキラはときどき頭痛の発作を起こすんです」ななめうしろからウーの声が説明していた。少年よりもゆうに頭ひとつ大きいくらいの長身だから声も太い。「すぐ治ります、ほっといていいです」
「ありがとう、ウー。でもほんとうなの、すごく辛そうだけど」
新しい先生を心配させてはならない。アキラは無理に身を起こし、顔をあげて笑顔をつくってみせた。
「よかった」ファン先生はこのひどく繊細な相好の小柄な児童をみてほほえんだ。「じゃ、つづけましょうか。でも気分が悪くなったらいつでもいってね」
やさしい声と表情がアキラの頭から痛みの残りを消し去っていった。
始業のチャイムが鳴る。新学年第一学期のさいしょの授業がはじまる。
「教科書を開く前に」新任教師は教卓から児童ひとりひとりをみわたした。「数学にまつわる軽いお話からはじめましょう。いまから二百年もむかしに生きた大数学者の、子供のころの話です」
児童たちはぽかんと口を開けた。かれらはこれまでいちども数学者というものをみたことがない。このこぢんまりした観光都市には大学も高等研究機関もないからだ。だからかれらの頭にあるのは、数学者とはむずかしいことをいつも考えている白髪の老人という漠としたイメージだけだ。そんなひとに子供時代があったことが新鮮な驚きだった。
「その大数学者がちょうどみなさんと同じくらいの歳のころ、小学校で」といって、教師は子供たちの興味をより惹きつける。「ある意地悪な先生が、鞭を振り回しながらこんな問題を出しました。1から100までのすべての数字を足し算して、できた者から手をあげなさい。もしまちがっていたらこの鞭でうんとぶっ叩いてやるからな」さいごの部分はまるで怪談に出てくるおっかない幽霊のような声色になった。子供たちははんぶんこわがり、はんぶん笑った。
またレオノールが挙手する。「子供を叩くなんて野蛮です」
「ええ、野蛮ね。でも、むかしはそれがふつうだったの」ファン先生はもとの若い女性らしい声に戻っていった。「いまの先生たちは殴らないかわりに、赤点をつけます」
子供たちはどっと笑う。ひとりアキラだけが笑えなかった。
「はい、お話を戻しますよ」先生は両手を打ちあわせて騒ぎを静める。「そのたいへんな足し算の問題にたいし、さいしょに手をあげたのは」
「もちろん、その大数学者でしょう」ウーが挙手していった。
「そのとおり」ファン先生は輝くような笑顔をウーに向けた。ウーのほうは誇らしげな笑みを返す。「しかも、彼はあっというまに答えを出したの。どうやったか、わかりますか」
つづけてウーが応じる。「そのひと、ものすごく暗算が得意だったんだ」
「そうね、たしかに得意でした」先生は大好きなひとについて語るように微笑しながら、教壇をゆっくりと行き来する。「ほんの十分でも空いた時間があったなら、楽しみのために計算をするようなひとでした。でも、そのときの彼が使った方法は、たんにすばやく足しあわせたわけじゃなかった。彼は頭のなかで、こんな計算式を思い浮かべました」チョークをとる。黒板には白い数字がみるまに並んでいく。
1+2+3+4+……+97+98+99+100
「なんだ、ふつうじゃん」ウーが不満げにいった。
先生はその反応を予期したように。「ここからがすごいんですよ」ふたつめの式をその真下に書き出した。
100+99+98+97+……+4+3+2+1
「いいですか、彼のすごいところは」ファン先生は黒板から児童たちを振りかえった。「さいしょの式をひっくりかえして、二番目の式をつくったことでした。ものごとをひっくりかえしてみることのできるひとはそうそういませんよ」
多くの子供たちは式の逆転の意図がわからずに首を右や左にかたむけていた。するとウーが。「あっ。そうか、ふたつの式を縦に足したんだ。横じゃなくて」
「ご明算っ」先生はチョークの粉で白く染まった手でウーを指した。ウーはうれしげに背筋を伸ばした。「すると、101が100個できますね。同じ数字を100回足すのは100を掛けることと同じで、ものすごくかんたんです。あとはそれを2で割ればいい」
先生はまた黒板を向いて、新たに短い数式を書く。
101X100/2=5050
「す、すっげえ」
「かしこーい」
「参りました」
「ほんとにおれたちと同じ歳かよ」
クラスメイトたちが感嘆の声をあげるなか、アキラは頭痛の復活を感じていた。
先生の話の要点はわかった。だいじなのは、ものごとをひっくりかえしてみること。だが、その要点を補強する細部があやふやだ。話の端々がぼやけてしまって理解不能だった。まるで板書の文字がかすれて読めないように。
語学力に問題があるわけではなかった。彼は英語、南欧語、中国語を母語と同様にあやつることができるのだから。
理解できないことを知られたくなかった。クラスのみんなに、なにより新しい先生に。少年は必死で周囲に同調し、わかったふりをする。
「では、いまの話を枕にして」先生は手を叩きあわせてチョークの粉を払った。「ひとつ、問題を出しましょう」
「えー」
「いやー」
「ふいうちー」
あちこちから不満の声があがる。ひとりウーだけが。
「待ってました」と、自信満々だ。数学は彼の得意科目である。きれいな新任の先生の前でかっこよく振るまうチャンスととらえているのはあきらかだった。
アキラは強まる頭痛に耐えていた。不安と緊張で動悸が激しくなってきた。やりすごせ、ウーかだれかに答えさせて。どうせ自分はわからないんだから。
「それでは問題。文章題だと思ってくださいね」ファン先生は節をつけて詩を唱えはじめた。
わたしがセント・アイヴスへ行くとちゅう
ひとりの男に出くわした
彼は七人の妻を連れ
妻たちはそれぞれ袋を七つ持っていた
袋にはそれぞれ猫が七匹入っており
猫たちにはそれぞれ子猫が七匹ずつ
子猫、猫、袋に妻たち
さて、いくたりがセント・アイヴスへ向かっていたのか
「さあ、答えはなんでしょう」先生は教卓にかたちのよい両手を置いて教室じゅうをみわたす。指輪はついてないぞ、と幾人かの男子が気づく。「わかったひとから手をあげてね」
子供たちは新任教師に応えたい一心で問題にとりくみはじめた。筆算でひたすら七を掛ける子が大多数。なかにはウーのように、さきほどの大数学者のエピソードに倣った華麗な解法があるにちがいないと頭をひねる者もいた。ところでアキラは。
わかってしまった。自分でも意外なくらいにあっさりと。
「先生」右手をあげた。数学の時間に進んで手をあげるなんてはじめてかもしれない。「ぼく、わかりました」
クラスはどよめいた。
「なんだって」
「は、はやい」
「どうせでたらめだろ」不満げな調子でいうのはウーである。「アキラは目立ちたいだけなんだ」と、自分を棚にあげる。
わきあがった騒ぎをファン先生は片手で制して。「アキラくん。答えをどうぞ」