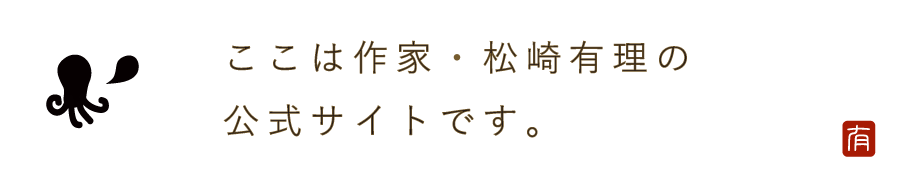作成日:2017/09/01 最終更新日:2017/09/02 かいたひと:松崎有理
一二五ダラーといえば、舞台鑑賞の料金としてはかなりの高額である。それでも超能力者ロクスタ師の秋公演チケットはまたも即日完売となった。
ロクスタ師の宣伝方法はつねにシンプルかつ効果的だ。今回のコピーは「あなたは奇跡を目撃する」。基本、事前情報はこれだけ。それでもひとは争ってチケットを求めるのである。二週間の公演を通して座席を押さえる熱心なファン、ないし信者も多かった。
会場は劇場街最大規模を誇るニューシティシアター。入口には物販があって、ここへも客の金がつぎこまれる。ロクスタ師の著書、師監修の超能力自己開発キットや悪い波動を防ぐという護符類。ネットワークの公式サイトから通信販売するばあいの数倍の価格なのに、山積みであった商品はすでに売り切れ寸前だ。公演時に入手すればより強い奇跡の力に触れられると信じられているためである。
前宣伝どおり、この夜かれらは奇跡を目撃した。公演初日の開演を告げるブザーとともにざわめきが止んで、客席側の照明が落ち、無人のステージに二千対の視線が集中する。ステージは通常の仕様で、舞台奥には大黒幕、袖には三重の黒い袖幕がついていた。数十秒も無音の時間が流れたあと、ふいに音楽。舞台両袖からスモーク。するとステージ中央に、トレードマークの白いローブをまとったロクスタ師の姿がとつじょ出現した。
観客は拍手も忘れて驚きの声をあげる。
「ようこそ」超能力者は両手を頭上に差しあげる。プラチナブロンドの長髪が、緑色の両目がスポットライトをあびて輝く。舞台映えする長身である。年齢は公表しておらず、神秘的な容姿から推察するのも困難だ。数千歳だとか不老不死だとか噂する信者もいる。「これより奇跡をおみせしよう。うしろのみなさんにも」
ことばを切ると同時にステージのライトが消えた。まばたきひとつするあいだに、ライトの位置が切り替わって後方座席の一点をまぶしく照らす。そこに立っていたのはまさしく。
「ロクスタ師だ」
すぐとなりの席に座っていた中年女性がふるえる手で彼のローブに触れた。「ほ、ほんもの。ああ、師よ」
自称超能力者は謎めいた笑みを浮かべて信者にこう告げた。「これが超能力。奇跡の力だ」
嵐のような歓声が劇場を埋めた。二千名の信者たちは叫び、手を振り、すでに涙を流しさえしている。
そのころ。
劇場通りをはさんで真向かいに位置するグランドスクエアズシアターでは、やはり二千名の観客を集めて奇術師ホークアイの秋公演初日が行われていた。チケットはやはり一二五ダラー。毎回、同時期に行われているロクスタの公演と同額に設定しているのである、意図的に。高価なチケットはやはり完売していた。三十代なかばにして芸歴二十年といわれるこの奇術師の人気は圧倒的だ。卓越した技術と高いエンタメ性に加え、貧しい先住民の子がスターダムにのしあがったというサクセスストーリーもこの国でうける要因であった。
とはいえ、こちらの会場では物販はない。奇術師の稼ぎは原則として演技への直接報酬のみであり、ロイヤリティには頼らない。本を書いたところで買うのは一部の手品好きくらいだ。また、驚きを味わうものという奇術の特質ゆえに、同じ舞台を繰りかえしみたがる客もほとんどいない。
今回の公演用に特設したステージは、客席中央に配した楕円形の巨大なテーブルにすぎない。何本かのコーン型の脚に支えられており、その下は素通しだ。開演のブザーが鳴っても、ステージも客席もこうこうと明るいままだった。注意をそらすための音楽もスモークもない。にもかかわらず、客たちがふと気づくとテーブル状の舞台の中央にトレードマークの民族衣装をまとった小柄な奇術師が立っていたのである。
「い、いったい、いつ。どうやって」
「ステージの下、なにもないよな」
「ずっとみてたはずなんだけど」
赤い肌の奇術師は黒い両目で客席をみわたした。またの名を、モヒ族さいごの呪術師。先住民の呪者の末裔であるという触れこみでデビューした。そんな売り出しであったにもかかわらず、彼は両手を差しあげて今回も観客たちにこう宣言する。その赤い手は体格に応じてちいさく、ポーカーサイズのカードなどぜったいに隠し持つことはできないようにみえた。
「魔法はけっして起こらない」
そのとたん、奇術師の姿は消えた。ひとびとは驚き、彼を探して明るい場内にせわしく視線をめぐらせる。たちまち。
「いたぞ。あそこだ」
数人の観客が、後方座席にひっそり座っている奇術師を発見して声をあげた。
「うそっ。と、となり」
「ぜんっぜん、気づかなかった」
両側の若い客は驚きのあまり口を開け、それから彼の衣装に触れた。「すごい。ほんものだ」「立体映像とかじゃないよ」
そのころ。
「ホークアイの圧勝だな。ま、ロクスタもすごかったが」
「すっげえな。ホークアイ、ロクスタがさいしょに瞬間移動をやるってどうやって知ったんだ。告知とかなかっただろ」
「それも含めて、やつの奇術なんよ」
「ちがうちがう、ホークアイのほうがほんとの超能力者なんだ。瞬間移動能力と予知能力があるんだよ」
「だから、奇術だって。本人がそういってるだろ」
ニューシティ市内に店をかまえるオサリバンズはいわゆるネットワークパブで、そのとき生中継されているネットワーク番組をみなでつっこみを入れながらみるというスタイルである。今夜も下町訛りまるだしの地元民たちがパイントグラスを片手にスツールに腰掛けてカウンター奥の大型モニタを指差し、口から泡を飛ばしていた。
画面は左右に二分割されている。片側にロクスタの公演、もう片側にホークアイの公演。画面の下部にはちかごろすっかり定着したショートコメントが流れている。自宅のネットワークで鑑賞しているひとたちが感想を短いテキストで送信しているのである。
ホークアイすげえ
今回もやってくれるぜ
種どうなってんだよ種
やつこそがほんものの超能力者
書きこみの総数があまりに多いのでいちどに表示されるのはランダムに選ばれた数行のみである。ふたりの対決を見守る人間の概数は受信する端末の数として画面上部にリアルタイムで表示されている。ディナータイムにもかかわらず八桁の大台に乗っていた。
カウンターのいちばん端っこでみごとな赤毛の男が夢みるように笑いながら映像をながめている。中背で、肌は白く目は青く、年齢は三十前後にみえる。そばかすだらけの頬もその髪のように真っ赤だが、酔っているわけではない。パイントグラスの中身は紅茶である。下戸なのだった。
「魔法使いだ」赤毛の男は夢みるようにいって、丸っこい指でグレーズのかかったドーナツをつまみあげるとひとくちかじった。店への食品の持ちこみは原則禁止なのだけれど、この男にかぎってはなんとなく黙認されている。だってうちはドーナツ置いてないからな、というのが店主のいちおうの理屈であったが、本音はこうである。だって酔いどれパディのやることだからな。
そのころ。
大統領から祝いの電話があったため、ワイズマン博士の二度目となるノーペル賞受賞記者会見は十五分遅れではじまった。場所は彼の所属するニューシティ高等研究所である。
割れんばかりの拍手とまぶしいフラッシュを全身にあびながら、ワイズマンは会場となった大講義室へ入ってきた。四十なかばの、研究者として脂の乗った年代だ。金髪、青い瞳、仕立てのよいスーツに包まれた長身はこの多民族国家で暗黙のうちに最上層階級とされる人種に特徴的な容姿だった。
成功した俳優かスポーツ選手のように、賞賛する記者たちをかきわけながら講義室前方のテーブルにつく。その背後には、百年前からノーペル賞級の科学者たちが理論や数式を書きなぐってきた古い黒板。左側の壁に切られた背の高い窓の外はすでに闇に沈んで、隣接するニューシティパークの照明だけがぽつぽつとにじんでいる。テーブルの右手に研究所長が立っていて、黒ぶちめがねの奥の離れた両目は誇らしさで泣き出しそうにみえた。
緊張ぎみな研究所長からの紹介を受けて、ワイズマンはマイクに向かって口を開いた。
「いやあ、二度目ですからね。すっかり慣れましたね、この大騒ぎも」
高IQ所持者であるのに不思議と嫌味のないジョークに、記者たちから軽い笑いがあがった。
十年前、三十代の若さでノーペル物理学賞を受賞したあと生物学に転向。本年みごとノーペル生命科学賞を受賞。彼は現代科学のアイコンとなったわけだ。この国の、そして世界の。
今回の研究成果について質疑がひととおり終わったあと、ワイズマンは記者たちをみわたして微笑を浮かべた。
「じつは。この場をお借りして、重大発表があります」
研究所長が分厚いめがねの向こうで眉をあげた。ワイズマンはいまにいたるまでだれにも計画をあかしていなかったのである。
フラッシュの洪水がおさまってから、受賞者は咳払いをひとつして話をつづけた。「本日。科学者として最高の栄誉である賞のふたつめをいただくことが正式に決定しました。生涯にいちどもらえればじゅうぶんとされるものを、ふたつも。わたしは思いました。自分は研究者としてはもうあがり、であると」
会場が静まりかえる。だれもが拳を握って偉大な受賞者のつぎのことばを待つ。
「ですから」ワイズマンの笑みはさらに大きくなった。青い両目は輝いていた。「わたしは本日をもって、研究活動から引退します」
一瞬、真空のような無音の時間が流れた。その直後、会場から驚きの声と嵐のような質問があがった。「そっ、そんな」「なんともったいない」「じゃあ、これからどうなさるんです」「休暇をとるのでしょうか」「それとも後進の育成」「著述活動ですか、公演ですか」「研究に戻ってくることもありうるんでしょうね」研究所長はめがねの奥で目をむいている。
ワイズマンは片手をあげて記者たちの騒ぎを制した。「とつぜんのことで申しわけない。みなさんの質問は、きっとこれに集約されるのでしょう。すなわち、わたしの今後の身の振りかた」
会場を埋める全員がうなずいた。研究所長も顎に深い皺をつくってなんどもうなずいていた。
「では。つづけて発表いたします」若干芝居がかったしぐさで拳を顎にあて、また咳払いした。マイクに口を寄せる。「わたし。ワイズマンは、研究活動引退後は疑似科学撲滅活動に力をつくすつもりです」
また一瞬だけ会場が真空になった。そのあと、またフラッシュと質問の嵐。ニュースはネットワークをつうじて全国を、全世界をかけめぐった。タイトルはおおむねつぎのようなものだった。
ノーペル賞ダブル受賞者ワイズマン博士、疑似科学バスターへ転向を表明
一時間強におよぶ初日の公演がはねて、観客へのあいさつと舞台の後始末を終えてスタッフたちと別れたあとキャブを拾おうとひとり劇場街の舗道へ出たところで、ホークアイのセルフォンが鳴った。
「はい」通話中を狙った物盗り対策のため建物のそばへ移動し、大理石の壁に背中をつける。奇術師が財布をすられたのではジョークにもならない。
電話の向こうの相手は名乗らずに笑った。その声だけでわかった。「ロクスタか。なんの用だ」
相手はまた低く笑った。「今夜もまた、やりすぎたと思っているな」
奇術師は沈黙を返した。
「ホークアイ。モヒ族さいごの呪術師にしてオカルトバスター」超能力者は低い笑いをまじえながら話しつづける。「このわたしの超能力を否定したいなら、奇術によってそっくり同じ現象を再現せねばならないはずだ。だがおまえは、今回もわたしの技を超えてみせた。みなは驚き、手を叩いて賞賛するかもしれないが、デバンキングとしては不完全だ」
ホークアイはまだ沈黙を守っていた。ここでことばを発したら負けだ。ロクスタはメンタリズムの達人でもある。方法は、ホットリーディングとコールドリーディングの技術の併用だ。おそらくすでにこちらのステージの録画を分析し、どこかのビルから動向を見守っている。ひとりになったところをみはからって電話してきたのだろう。いまも電話ごしの呼吸音や間合いで感情を読んでいるにちがいない。
五番街をはさんでそびえるビル群をみあげる。ホークアイの視力は両目とも四・〇で、かつ夜目も利く。だが明るい窓にも暗い窓にも屋上にも、彼を見張る者の姿は発見できなかった。電子的手段で離れた場所から監視しているのか。
オカルト詐欺師たちがどれだけ入念な仕込みをするかはよく知っていた。ひとりのカモの心をつかむために数年かけて身辺を調査するなんてざらだ。それをいうなら奇術師の下準備への執念も似たようなものだった。たとえば、クローズアップマジックの父と呼ばれる奇術師マックス・マリニは、だれかの家に招かれるたび額縁の裏やソファのすきまにこっそりトランプをいちまい隠していったという。何年先になるかわからない再訪時にカードマジックを披露するためだ。
オカルト詐欺師と奇術師の考え方はとてもよく似ている。硬貨の裏表のように。
「いいか。わたし、超能力者ロクスタは予言する」電話の声はより近くなったように感じた。「いつかおまえは、その点で失敗する。みずからを頼むその驕りが、いずれかならずおまえを滅ぼすだろう」
「じゃあ、こっちも予言してやろう」ホークアイはようやく口を開いた。「自分こと奇術師ホークアイは、ロクスタはじめすべてのオカルト詐欺師どもをいつか完膚なきまでに叩きのめす。おまえたちの終わりはいずれかならずやってくる。楽しみにしているんだな」
相手は笑った。梟の声に似ていた。ホークアイはセルフォンを耳から離して通話を切った。