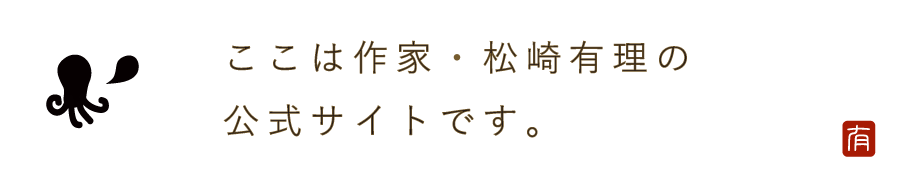作成日:2017/09/03 最終更新日:2017/09/06 かいたひと:松崎有理
その男は緑色の瓶の中身をぼくの頬に塗り終え、満足げな笑みをうかべた。三十歳くらいのさも賢そうな男前で、ふだんはめったに笑わない。
「おまえはもう一生結婚することができない」
ぼくの目をのぞきこむ。また笑う。美形なだけにいっそう怖い。
負けるもんか。負けないぞ。なにが呪いだ、呪いの正体とは思いこみだ。信じさえしなければなんの効力もない。
大声でそう叫んでやりたかった。だが口は開かない。そもそも全身にわたって、まったく、指先さえも動かすことができなかった。
あああああああああ。かわりに心のなかでせいいっぱい叫んだ。あああああああああ。動け、このからだ。声を出すんだ。声を。あああああああああ。
「あああああああああ」
勢いよく布団を払いのけて起きあがった。短距離を全力疾走した直後のように肩が上下していた。心臓が跳ねている。寝間着がいやな汗で濡れている。
あの夢か。ひさしぶりだな。
見慣れた古い貸間の古い柱と古い掛け時計をぼんやりながめながら、夢の内容を反芻した。ふだんは忘れ去っているけれど、春がくるころかならず夢のかたちで記憶がよみがえる。三年前のこの季節、代書屋としての初仕事。依頼人は意地悪な研究者。ぼくはまだ依頼人との適切な距離のとりかたを知らず、反発したあげく彼の研究主題でもあった呪いをかけられるはめになった。しかも。
結婚できない呪いだ。
はああああ、と長いため息をつく。あれから三度めの春がくるけど、ぼくももう二十六歳になるけれど、結婚どころか恋人ができるきざしすらないのは呪いのせいだなんて思いたくはない。
片思いしては振られ、また片思いしてはあきらめて。いったい何敗したのやら、そもそも勝てたためしがない。
ああ、一回くらい女性から惚れられてみたいよなあ。
もうひとつため息をついて布団からはい出す。窓際に寄る。窓覆いをつけていないので早春の日射しが硝子を通して室内にふりそそいでいる。床の陽だまりには手のひらに載るくらいの鉢、その中央にちんまり座っているのは親指ほどのさぼてんだ。
「おはよう」と声をかける。とはいえ、さぼてんはきわめて無口だからけっして返事をしない。ただだまって白い棘を朝の光に輝かせているだけだ。
なんだろう。いましがたの夢のせいか、しゃべらない相手にまいあさ声をかけ、毎晩さしむかいで食事をするのもなんだかむなしく思えてきた。高性能炊飯器や自律式掃除機を自宅で恋人か嫁のようにあつかっている独身者の話、ぼくは笑えない。それどころか泣けてくる。
思えばこのさぼてんは、あの呪いを受けたころ片思いしていた相手から贈られたものだった。超現実な雰囲気がきわめて印象的な女性で、きわめて印象的な振られかたをした。ぼくを遠ざけるため超現実なふるまいを演じていたのである。でもあの失恋はさぼてんのせいじゃない。あれから三年、この植物はずっとぼくの寡黙なともだちでいてくれている。
鉢の前に正座し、目を閉じて神に祈る。神といっても教会や寺院にまつられている有名なものではない。ぼくがつくった、ぼくだけの神。ミクラ専用神というわけだ。ぼくの脳内に住んでいるのは幻影みたいな仮の姿で、本体は遠い南の島にいる。名前は、アカラさまという。現地語で「空気も行間もよめないもの」という意味だ。金泥で隈取りした赤い面をかぶり、後頭部はつるつるで前髪だけが長い。
アカラさま。どうかぼくにすてきな結婚相手をさずけてください。
だが前髪の長い神は、波打ち際に尻をつけて座りこみ白い砂で無心に城をつくっている。ぼくの祈りがきこえているとは思えない。
たいしてがっかりするでもなく目をひらいた。だいたい、ぼくが四歳のときから脳内にいるくせにあの神はこれまでなにもしてくれたことがない。ただ見守るだけの神だ。見守ることさえさぼったり、たまに家出してしばらく帰ってこなかったりもする。
「さて、と」自分をはげますように声を出す。ぼくにしてはずいぶん早く目が覚めた。さっそく営業に出かけよう、脈がありそうなあの場所へ。
あのひとに会うのもいち、にい、さん、と、五日ぶりだ。ほんとはまいにち顔をみたいけれど、忙しい相手をひんぱんに訪うことはできない。それに会えないあいだのせつなさも悪くないと思う。
にわかに機嫌がよくなって、鼻歌をうたいながら布団をたたむ。悪夢は、しょせん夢にすぎない。呪いなんて信じさえしなければ、呪いではない。なんだ、あんな非科学的なもの。これまでぼくの恋が成就しなかったのはたんなる悪い偶然の積み重ねなんだ。
上機嫌なまま黒の上下に着替え、せまい台所の横のせまい洗面台で入念に髪をとかす。このあと自転車に乗るからむだになってしまうのだけれど、そうしたい気分だ。だから、いい。
背囊型のかばんを背負い、貸間の玄関を出る。朝の空気はきりっと冷えてほんのり湿気をふくんでいる。軽い足どりで建物の東側にある駐輪場へ向かう。彗星号はきょうも薄い屋根の下で車体をなめらかに輝かせながら待っていた。
「おはよう」
座面をぽんぽん叩く。その音で相棒がいかにごきげんかわかる。大学に入ったばかりのころせっせと時間給の仕事をして買ったこの自転車ももう八歳。まいにち乗って年季が入っているが、手入れがいいから状態は良好だ。山道も走れる軽量強固な型で、材質のためか傷はとてもすくない。
「それいっ」声をかけて四十八号線に乗り出す。快晴で、日射しだけは春らしくまぶしいけれど風はまだ冷たくて耳を持っていかれそうだ。ぼくと彗星号は一体となって走る。ゆるい下り坂も手伝って速度は順調にあがっていく。さあ、もう自動車にだって負けないぞ。
「っおおっと」だが荷を積んだ大型車にあおられて、しかたなく車道の端へよけた。この道路は交通量が多く、二輪車はどうも分が悪い。
四十八号線から右へ折れると、道はいきなりせまくなり傾斜がきつくなる。おかげで大型車両は消える。ぼくらはさらに速度を増して、その勢いで四度見橋をわたる。橋の下は北の街の象徴、廣瀬川だ。川面にはいまだ旅立ちを躊躇している冬鳥たちがぽかりぽかりと浮かんでいた。
古人の歌をちょっともじって、自作の節をつけてうたう。
われのこころは
廣瀬の水よ
わがままきまま
流れてゆかう
うたいながら青信号の交差点を越える。春休み中の部活動にむかう運動着姿の高校生たちがけげんな顔で振り返るけど、気にしない。ほら、もう目的地だ。河岸段丘にひろがる蛸足大学文系地区は目の前だった。
ところが。
「し、しし、し。ししし失踪ですって」
心理学研究室教授のはんぶん白い眉は両端が下がっていた。「どうやら、そういうことらしい」すっかり疲弊したような声だ。
研究室は閑散としていた。大学もいまは春休みだ。田の字をつなげたかたちにならぶ学生用平机にはだれひとり着席していない。だから奥の小部屋から教授が出てきてぼくに応対してくれる。秘書を雇う余裕がないのは知っていた。
この研究室は小さな所帯で、常勤の構成員はこの教授と、去年着任したばかりの若い助教のふたりだけだ。若いといってもぼくよりよっつ上だが。
「失踪って。助教は、い、いつから姿がみえないんですか」
「さいごにみたのは五日前だ。それまでほぼ毎日、週末だって研究室にきていたのに。自室に電話してもずっと留守電なんだよ」
五日前。忘れもしない、前回ここを訪れた日だ。ふだんどおりに彼女は自分の席にいた。ふだんどおりに忙しく仕事をしていた。椅子からぼくを振りあおいで、研究は佳境に入っているといった。そしてこうもいった。
つぎの論文の執筆、ミクラくんに手伝ってもらおうかな。
それをきいて、仕事を受注できるという理由に加えて体の芯から震えるほどのうれしさを感じたっけ。
あのとき彼女に失踪の徴候などなかった。
教授室の手前の大きな机、あそこが彼女の席だ。たしかにいまは無人だった。机のうえには重たげな学術書や愛用の筆記具が、椅子の座面にはいつもの赤い膝掛けが載っていて、ここの主はいまちょっと席はずしてるだけですよ、と口をそろえていっているようにみえた。
助教。容姿からして、目をはなしたすきにふうっと消えてしまいそうなひとだ。猫みたいにふわふわした茶色の髪、求肥のようにやわらかそうな白い頬。手などは繊細なつくりの人形みたいだった。うっかり触れば壊してしまいそうな。夢のなかから、あるいは童話の絵本から抜け出てきたような。歳上だが、とてもそうは思えない。
心配だ。
教授に数歩つめよった。「失踪って、どういうことですか。警察にもう連絡は」だが警察、という自分のことばでわれに返った。ちょっとまて、落ちつけ。助教だっていい大人だぞ。大学が休みの時期にほんの数日姿がみえないからっておおさわぎすることもないはず。
落ちつけ、落ちつけ。大きく息を吸って、長く吐いた。おかげで脳に酸素がいきわたって冷静になれた気がした。そうだ落ちつけ、教授のふるまいに流されるな。彼はとびぬけて悲観的で心配性だ、皮肉なことにこの研究室は前向き思考心理学を扱っているのだが。「落ちついてください。失踪なんておおげさです。たとえば、急用で実家に帰ったとか」
「ご実家には電話してみたよ。しかし」教授ははんぶん白い頭を横に振った。いなかったようだ。
「友人関係は。仲のいいともだちのところに転がりこんでいるのかも」この点、ぼく個人としておおいに興味がある。
相手はやはり首を左右に振る。「それはないだろう。彼女は去年こちらに赴任してきたばかりだから、まだそこまで親しい友人はいないようだ」
不謹慎だがちょっとうれしくなった。
「それじゃあ、たんに骨休めをしたかったのでは。ちょうど大学も春休みだし」多くの研究者は休みのときほどよくはたらく。講義や会議や学生の指導から解放されて研究に専念できるからだ。でもそんなんじゃ燃えつきちゃうだろう。
「休みたい、か。気持ちはよくわかる」眉の下のちいさな目がますますちいさくなる。目尻には涙さえ浮かんでいた。悲観主義者さもありなん。「わたしも悪かったのだろうね。彼女の多忙さを知りながら、つい、わたしだけではこなしきれない雑用をたくさん振ってしまった。追いつめてしまったのかもしれない」
ぼくは深くうなずく。
昨今の研究者たちの異常な忙しさには原因があった。それも明確な。
出すか出されるか法。長すぎるためだれもつかわない正式名称は、大学および各種教育研究機関における研究活動推進振興法。
三年ごとに査定がある。論文を一本も書いていない、または書いていても本数や質が基準に達していない研究者は即、解雇される。
つまり。論文を書かない研究者は去れ、といっているわけだ。
この法律が施行されて四年が経った。昨年ついに行われた第一回の査定により、予想をはるかに超えた大量の解雇者が出た。生き残った者たちは震えあがり、よりいっそう論文の量産にはげむようになった。
追い立てられるように。しっぽに火のついた猿みたいに。
だからぼくのような論文執筆代行業者が存在している。通称、代書屋。多忙な研究者たちに代わって研究成果をまとめ、学術雑誌に投稿して対価をもらう仕事だ。かけだしのぼくでさえごはんを食べていけるのはこの法律のおかげでもある。だからぼくらの立場では、あしざまにはいえない。
しかし、研究者たちの忙しさの要因は論文の執筆ばかりではなかった。ここがさらなる問題点だ。
論文を書き、学術雑誌に投稿する。すると雑誌側は、投稿された論文が掲載に値するかどうかを検討する。これを査読という。一流半以上の雑誌はこの方法を採用して質の悪い論文をうっかり載せないようにしている。ところで査読作業ができるのは当該分野の研究者だけだ。しかも査読は名誉な仕事とされ、無報酬で依頼される。そして評価が独断におちいらないよう、一本の投稿論文にたいし査読者は二名ないし三名があてられる。
論文の投稿数が増えれば、すなわち無償の査読作業も増える。
代書屋として研究室に出入りし、横目でみているだけでも状況のきびしさは伝わってきた。研究者たちの机には雑誌編集部から回されてきた投稿論文の写しが積みあがり、査読を待っている。講義や会議や実習や卒論修論の指導や学会や出張や研究室の備品の発注や試薬の管理や各種申請書類づくりや、もちろん自身が研究したり論文を書いたりする時間をけずって、この名誉な仕事をかたづけねばならない。しかも誠心誠意。なにせ名誉な仕事だから。
どうやって時間を捻出すればいい。かれらは悲鳴をあげていた。とくに常勤職についたばかりの若い研究者に負担が大きかった。立場上、雑用をまかされやすいからだ。
逃げ出したくなる気分もわかる。どこか遠くへ、だれも自分を知らない土地へ行ってみたくもなるだろう。周囲には告げず、ひっそり、とつぜん。
まてまてまてまて。そういうのを失踪というのでは。
「助教は、いったいどこへ。手がかりはないんですか」彼女の机に飛びつき、紙片という紙片をひっくりかえす。文献の複写、教務から回されてきた書類、来年度の講義予定表。失踪を匂わせるものはなにもない。
「ちょっと、失礼します」
すぐ横の扉をあけて教授室に入る。ひとの命がかかっている、少々の無遠慮はしかたない。教授もとくにとがめることなくついてきた。
二畳ほどの、ほんの小部屋だった。巨大な書き物机が部屋の半分を占めている。のこりの半分は書棚。蔵書はもっと持っていそうだが、自宅や貸し倉庫に分散して置いているのだろう。机のうえは研究者にありがちな、目を覆いたくなるような惨状だった。ひらいたままの専門書や学術誌が数十冊もかさなり、そのあいだに書きかけの原稿、図表や写真、おびただしい書類、封を切ったり切らなかったりの郵便物、反故紙に書きつけた覚書き等が、くしゃみひとつでなだれをうって流れ出しそうなあやうい角度で積みあげられている。
ほ、崩壊寸前。
一瞬ひるんだけれど、捜査の手をゆるめるつもりはなかった。「失礼します」もういちどいって、紙の山をかきわけはじめる。
「ああっ。場所、動かさないで。なにがなんだかわからなくなる」机の主が悲痛な叫びをあげるが、かまってはいられない。
ところが捜査はわりにあっさり終了した。「これは、なんでしょう」山の上部から便箋をいちまい、つまみあげて相手につきだす。折れ目も汚れもない、あきらかにごくさいきん書かれたものだ。
「なになに」教授は目を細め、手にした便箋をこころもち遠ざけて内容を読みあげた。「研究のさいごの詰めをするため、調査にいってまいります。春休みが終わるまでには戻りますのでどうかご心配なく」
「これ。書き置き、ってやつじゃないんですか」ひややかな声を出してみた。
「そういえば彼女。調査にいきたがっていたから、春休みならいいよ、って許可したんだっけ」教授はようやく安心したように笑い出す。「すまん、すまん。それでなくても年度末はたてこんでいてね、つい」
よかった、失踪じゃなくって。
ひとまず安堵するも、論文を量産するため春休みを調査にあてる多忙さにまた胸を痛めた。もっとも研究が好きなら苦にしていないかもしれないけれど。「机のうえを汚くしておくから、せっかくの書き置きに気づけないんですよ。それから老眼が進んでいるならめがねをつくってください。それと、予定の管理がご自分でできないなら」秘書を雇って、とつづけたかったが飲みこんだ。金銭的にむりだとわかっているからだ。
机上の乱した部分を可能なかぎりもとに戻す。とはいえもとから乱れているのでどのていど復元できたかわからないが。「さてと。これで一件落着ですね」
春休みじゅう彼女に会えないのかあ。さびしいなあ。会うことを自粛しているのとは気持ちのうえでぜんぜんちがう。
でも、しかたない。またせつない気持ちを抱えて指を折り日付を数えるよりない。「それでは。助教が帰ってくるころ、こちらにはまたうかがいま」
「あああ。しかし。でも」ふたたび教授は悲痛な声をあげた。「春休みは残りたった二週間。それまでに調査を終えて、ぶじ戻ってきてくれるだろうか。なにせ、仕事が。ああ」天井をみあげて固まってしまった。自分の双肩にのしかかる膨大な作業量を想像して思考停止におちいったのだろう。助教の調査行の予定を失念したせいだから自業自得なのだが、それでもちょっと同情する。
調査行か。失踪じゃないのはよかったけど、助教、だいじょうぶかな。
あの、ほうっておくと消えてしまいそうな。はかなげな。たよりなげな。
彼女との出会いはとにかく印象的だった。いまから数か月前、冬になったばかりのころだ。経済学部の依頼人との数時間におよぶうちあわせを終えたあと、遅めの昼食をとろうと文系食堂に入った。矩形の盆を持ち、厨房と直接つながる棚から料理の皿に手をのばしたとき。
だれかの手があたった。
「あっ。すみません」
あわてて手をひっこめ、振り返った。うしろに並んでいた小柄な女性がおなじ皿をとろうとしていたのだった。
その色白の女性ははにかみながら謝罪してきた。「ごめんなさい。考えごとをしていたもので」恥ずかしげに頬を染め、上目づかいにぼくをみるその表情がまことにかわいらしかったので。
「い、いい、いいえ。お、おかまいなく」
返答はひどく不自然な口調になってしまった。「こ、ここは大学だし、考えごとに夢中になっていろんなことをやらかすひとであふれてますから。手があたるくらいかわいいもの」
と、会話をつづけようとしたが彼女はすでにほかの皿をとろうと爪先立ちで棚にちいさな手をのばしていた。
すると。「あっ」彼女はほうれんそう胡桃和えの小鉢を落としかけた。いそいでぼくが食器をうけとめる。
「ごめんなさい」相手はまたはにかんで謝罪する。いやいや、こんなひとなら迷惑だなんて思わないって。
そのあともろもろ料理を載せた盆を持って支払所にならんでいると、彼女がやってきてぼくのうしろについた。背後を意識しながら小銭を数えていたら、彼女はまた小声で「あっ」といった。
支払所のおばさんに代金をわたしてからきいてみる。「どうしたんです」
相手はまたしても白い頬を染めた。そして細い声で。「お財布、研究室に忘れてきちゃった」
うちのめされた。やられた、こっちの負けだ。完敗だ。脳内ではアカラさまがぼくの心臓に直結する鐘を力いっぱい連打している。ふつう食事しにきて忘れるか財布。なんて現実ばなれした、こんどこそほんとうの。
超現実だ。
もちろんぼくは彼女のぶんを払った。おごってあげてもよかったけど、貸したことにすれば彼女の研究室に行く口実ができる。こういう小技がつかえるていどにはぼくも成長していた。さいしょ彼女は学生なのだろうと考えていたから、自分より歳上の教官だと知ったときにはその意外性にまたうちのめされてしまった。この嘘でも演技でもない超現実ぶり、これはぜったい運命だ。まちがいない。
思えば、代書屋のぼくが顧客となる研究者に本気で惚れてしまったのははじめてだった。それもまた意外で、不可思議で、いっそう彼女に惹きつけられる要因となった。
たしかに彼女は研究者として有能だ。三十歳という若さでこの古い大学の常勤職を射止めた事実が証明している。そのぶん性格もじつに研究者的で、集中的に考えはじめたら浮世のことなど忘れてしまう。卵をゆでるつもりで時計を煮てしまうようなひとだ。財布を忘れるのはしょっちゅうで、お茶を淹れようとして急須に鉛筆削り器のなかの削り屑を入れていたのをあわてて止めたこともある。なかなか講義室に現れないので学生が探しにいったら階段にひと足かけた姿勢で固まったまま考えごとにふけっていた、なんて話も耳にした。ぼくはそれをきいて、乗合馬車の踏み段に足をかけた瞬間にとある難問の解決方法を思いついた一世紀前の有名な数学者の逸話を思いだしたものだ。
現実から遊離している。どうにも不器用で、たよりない。ほうっておけない。
あんな女性がひとりきりで調査旅行なんて、だいじょうぶだろうか。教授の心配性が伝染したわけじゃないけど、やっぱり心配だ。
きめた。
「ぼく、助教を探してきます」