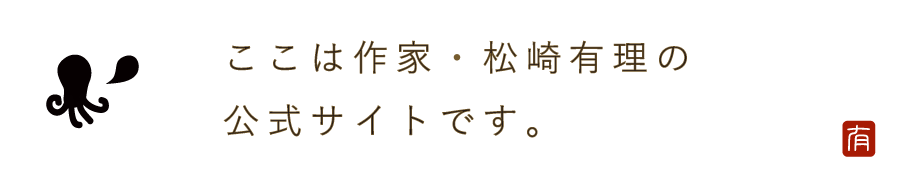作成日:2017/09/20 最終更新日:2017/09/26 かいたひと:松崎有理
るるるるるる。るるるるるるる。るるるるるるる。
無人の部屋で電話が鳴る。
るるるるるる。るるるるるるる。がちゃ。
呼び出し音はついに切れて、機械音声が応答をはじめた。「ただいま留守にしております。ご用件をどうぞ」
「えええ、朝からすまんね」二度ほど、咳払い。老いた男の声はつづく。「ああ。シーノくん、いないのかい。ええ、こないだの話のつづきだよ、いい話。うん、あのね。ひょっとしたらきみに、ホラホラ属分類の研究職を紹介できるかもしれないんだ。えええ、それでね」
ぴーーーーーーーー。
録音可能時間は無情な電子音とともに終了した。
室内はふたたび無音になった。ついさきほどまで暖房されていた空気がじょじょに冷えていく。
窓の外では雪片が舞っている。北の街は真冬をむかえた。
そのころ。
シーノが蛇足軒に出勤すると、すでに仕事をしている者がいた。
ゔーん、ゔーんゔーん。
少々耳障りな音を発しながら、それは居間の床の上をじれったいほどゆっくり走り、壁ぎわでぽにぽにぽにぽに、と電子音を出してからくるりと回って、さきほどとはちがう経路で、また床をなめるかのようにゆっくりと走り出した。
みれば、そのひとかかえほどの低い円筒型の胴体下部ではちいさな帚が高速回転している。ゔーんゔーん、と音がするのは、床から空気とともにほこりを吸引しているためらしい。
あ。自律型お掃除機械。
開け放った襖の前でシーノは合点した。 家電量販店でしばしば実演している。じぶんで考え、判断して部屋をきれいにする。高度な人工知能を搭載しており、人間が指示せずとも日々の役目を果たす。掃除が終われば集めたちりをみずから廃棄し、じぶん自身を充電さえする。
おまかせできるかしこさです。そんなうたい文句の商品だった。
雇い主が買ってくれたのかもしれない。シーノの顔はほころぶ。ちいさな建物とはいえ日々の掃除はめんどうだ、かわりにやってくれる機械がいるとすごくたすかる。
長卓の脚のまわりを帚でしつこいくらいていねいにていねいに掃除していた機械は、ぽにぽにぽにぽに、という電子音をふたたび出して、動きをとめた。本体中央の丸い釦が緑色に光った。
「おはようございます」
シーノは目をむいた。こいつ、しゃべるぞ。
「はい、ぼくは話せます」お掃除機械は相手の沈黙を驚きのための絶句とただしく解釈したようだった。「こわがらないでください。ぼくは市場に出ていない最新型なのです」男とも女ともつかない、変声前の少年みたいな声だった。ただし、ことばづかいはひじょうにていねいだ。
はああ。しゃべる機械だなんて、未来社会を描いた空想科学小説に出てくるようなものがついにできあがったのか。
そっか。未来って、いまだ。
そう考えればこれまでつちかってきた科学的常識とは衝突を起こさなかった。
「音声入力も可能です」機械はさらにつづける。口調は小説で描かれる典型のように平板ではなく、自然な抑揚があった。「指示がなくとも働きますが、よろしければなにかご命令ください。この部屋をもっと重点的に、とか、つぎの部屋に移れ、とか」
え、えっと。それじゃ。
シーノはまだ脱いでいなかった外套の襟をかきよせた。それじゃね、暖房つけて。
みじかい円筒型の機械は半回転し、緑色の釦を点滅させた。首をかしげた動作を模しているとはっきりわかった。
ああそうか。この子、お掃除しかできないんだ。
シーノは居間を横切り、壁の釦を押した。天井近くに設置された空調機からあたたかい風が吹き出してきた。
お掃除機械は右に左にゆっくり首を振るようにして回転しながら緑の釦を点滅させていた。そしてシーノの足元まですべるように近寄ってくると。
かしっ。本体下部から白く細い可動性の腕がのびた。先端にはたきがついている。そのはたきの頭の部分で。
空調機の釦を押した。風がとまった。また、押す。ふたたび温風が吹き出す。
ぽにぽにぽにぽに。掃除機は納得したように緑の釦を点滅させて、はたきの腕を収納し、一回転した。うなずいたみたいにみえた。「学習しました」
シーノは再度、目をむいた。
第三十三代蛇足軒はいつものように昼をまわってから居間にあらわれた。
いつもの所作できせるのたばこに火をつけ、さもうまそうに三口で吸いおえた。それから、長卓のむかいに座っている秘書と、床のうえで動きをとめている低い円筒型の機械をみた。掃除機は釦を緑色に点灯させて、まるで座ったまま耳をすませているようにみえた。
「うん。彼ね、きょうからあずかることになったんだ」
彼。ひと扱いか。まあ、わからないでもない。
それと、あずかる、って。買ったんじゃないの。シーノは首をかしげる。
あっそうか、市場に出てない最新型なんだっけ。実地試験かな、どこかから頼まれて。
「職安に頼まれてね」
ぽにぽにぽにぽに。機械はその場でくるりと一回転し、釦を点滅させる。
なぜ、職安。
秘書のあがった眉をみて、蛇足軒は説明をつづけた。しかし意外な説明だった。
「彼、特殊求職者なんだよ」
えええええっ。
シーノはまたしても目をむいて、雇い主と自律型お掃除機械を交互にみた。いや、その。たしかにこれまでにも、人間じゃない者が特殊求職者としてここにやってきたことはあった。しかし彼のばあい、ほぼ人間だったわけで。いまも人間として元気に百貨店地下高級食品売り場で働いてるし。
だけど。
もういちど掃除機をみやる。きょくたんに背の低い円筒型。点滅する釦。車輪で走行。機械だ。どうみても機械だ。
人間じゃない。
「やはり、むりだと思います」彼女の動揺を察知したのか、人工知能搭載掃除機は少年の声でしゃべりだした。「ぼくは人間の姿をしていません。人間がするような仕事ができるとも思えません。ぼくにできるのは、人間にはとてもやれないほどのていねいなお掃除だけです」
「そんなことない」職安特命相談員はきっぱり首を振った。黒いまっすぐな髪が肩先で揺れた。「だってきみ、りっぱな教育を受けて博士号まで持ってるじゃないか」
えっ。
と、シーノは驚きかけたが、ここですでに半年いじょう勤務している経験が彼女を押しとどめた。ちょっとまて、このひとは職安特命相談員である前に嘘道百歩七嘘派家元だ。だからきっとこの話も。
「はい。たしかにぼくは蛸足大学文学部心理学研究科博士前期課程を一年、後期課程を一年半で修了し、博士論文『人工知能によるヒトの心理分析』で博士号かっこ心理学かっことじ、をいただきました」
えええええっ。
こんどこそほんとうに驚いた。彼は機械だ、嘘をつくわけがない。
掃除機をあらためてみつめた。博士課程は前期二年、後期三年で合計五年。これが博士号をとるまでの大学院教育で通常必要とされる長さだ。じぶんもそうだった。期間を短縮できなくはないけれど、図抜けた能力の持ち主にかぎられる。たとえば蛸足大学理学部では、シーノの在籍期間中に飛び級をはたしたのは数学科にひとりいただけだった。
たしかに、大学教育と大学院教育は博士増員十万人計画施行によって破壊的にぬるくなった。しかしそれは定められた年限で、あるいは年限以上をかけて卒業するばあいだ。飛び級は別格である。この制度にはありし日の教育の良心が残っている。
それほどたいへんなことなのに、この子は。
ぽにぽにぽにぽに。機械は釦を点滅させながら、右へ左へ半回転した。首を振っているのだ、とひとめでわかった。「でも、持ちあげすぎです。いまや価値の暴落した博士号など持っていてなんになるでしょう」
シーノのたましいに研ぎたての巨大な包丁がぶっつり刺さった。
「いやいや。きみの所属していた研究室に電話してみたんだが、教官のみなさんはそろってきみの優秀さをほめていたよ。指導教授はたいそうきびしい方で、博士増員十万人計画施行後もこれとみとめた学生にしか博士号を出さないことで有名だそうだね。誇っていいと思うよ」
「いえ」相手は弱々しく釦を点滅させた。「持ちあげすぎです。だってぼく、お掃除機械にすぎませんから」
会話ができても、教育を受けても、博士号をとっても、やはり人間ではないのです。
ふむ、といって蛇足軒はあごに手をあて、特殊ちゅうの特殊求職者をみつめた。
シーノも人工知能搭載お掃除機械をみつめていた。受け答えもふるまいも、たしかに人間っぽい。しかし、あきらかに、人間じゃない。そうだあれは掃除機だ。なのに。
なぜだか胸のなかがざわざわした。
「はい、名前はありません」特命相談員の問いにたいし、特殊求職者である掃除機は少年の声でこう答えた。
「それじゃ不便だろ。心理学研究室では、なんて呼ばれてたの」蛇足軒はたばこを終えて、さきほどシーノが淹れてきた珈琲をすすっていた。
ぽにぽにぽにぽに。釦が点滅する。「990です。型番ですので」
あっ、ほんとだ。
本体上面の釦のすぐそばに、その番号は白い活字でちいさく刻印されていた。
「シーノ」雇い主が視線を投げてきた。
えっ。えっと。それじゃ。
ぽにい。
「そのまんまじゃない」家元は碗のうえで苦笑した。「うん、でもまあ、いいか。特徴をよくとらえてるし」
「問題ありません。ありがとうございます、シーノさん」ぽにい、と名づけられた掃除機は礼儀正しくいって、ゆっくり一回転した。お辞儀なのだろう。「番号ではない名前をいただいたのははじめてです」
いえ、どういたしまして。シーノもお辞儀を返す。
「ねえ。ぼくもまだくわしく知らないんだけど」蛇足軒ははんぶん空いた碗を置いた。「経緯を話してもらえるかな。それをきかないと、どんな仕事を紹介したらいいかわからないからね。まず、ひとつめ。人工知能搭載の最新型掃除機が、なぜ心理学の博士号をとったのか」
「はい。人間心理に興味があったからです」ぽにいは釦を強く点灯させた。胸をはったようにみえた。「人間の判断は、ときに非合理的です。前後の行動の矛盾や、言動不一致などもしばしばです。ふしぎです。謎だらけです。もっと知りたい、と思いました」
む。りっぱな受けこたえだ。これなら大学院の面接試験も余裕だろう。シーノはそんな感想を抱き、なぜだかまたざわざわした。
特命相談員の質問はつづく。「そしてふたつめ。博士号をとったのに、なぜ職安に頼ることになったのか」
じぶんもそうだ。シーノは苦笑して、ようやくちょっと安堵する。そして安堵を感じているじぶんをふしぎに思う。たしかにきみょうだな、人間心理。
「えっ。ああ」ぽにいはひじょうに人間くさく口ごもって、釦をはげしく点滅させた。ことばのかわりにぽにぽにぽにぽに、という電子音がけたたましく鳴った。「あああ。えええええ。その」きれぎれに感嘆詞を吐いて、その場でぐるぐる回り、ひとしきり回ると逆回転をはじめた。そして。
「えええええええええ」ぽにぽにぽにぽにぽにぽにぽにぽに。
付属の帚を高速回転させながら居間の床を全速力で駆け抜けて、壁のそばに設置されていた充電器にがちゃりっ、と大きな音を立てておさまった。釦の光は緑色から橙に変わった。
「しまった。単刀直入すぎたか」蛇足軒はやせた手を頭のうしろに回した。「あの子、心的外傷があるって職安相談員がいってたんだよね。過去のことをたずねるときにはくれぐれも慎重に、って」
ああ彼か。じぶんの就職相談担当であり蛇足軒への直接の依頼担当でもある若い男の感じのよいほほえみを思い浮かべる。ふちなしのめがねと軽く逆立てた髪も。役人らしくない。
この男も。目の前の特命相談員に視線を戻す。
「それでねシーノ」雇い主は身を乗り出した。「ひとつ、おりいっておねがいが」
きたな。彼女は身構える。
「ぽにいのめんどうをみてくれ、とまではいわないけど。しばらくここでいっしょに仕事して、ようすをみててほしいんだ。できればおりをみて、ちょっとずつ彼の過去を質問できるといい。いやシーノにはむずかしいか。質問はぼくがするから、それまでに彼の精神がそれなりに安定しててくれるとうれしい。そういうふうにしむけられるかな」
なにその難題。
心的外傷をかかえた機械の心をいやせ、と。
「心。うん、そうだね。彼にはきっと心があるよ、すくなくともよく似たものが。なにせ最先端の人工知能だから」
機械相手に臨床心理士のまねごとなんて。自信ないです。
ところが相手は自信まんまんで片側の頬にえくぼをつくっている。「だいじょうぶ、きみならできるよ。むしろ最適だと思う」
なぜ。
思いきり眉をよせ首をかしげたが、この大仰な疑問のしぐさにもかかわらず。
「じゃ、よろしくね。そうそう腹減った。あまんざで菓子買ってきてくれるかな」
と、みごとにかわされてしまった。
疲れた。ふだんよりずっと。
夕方。食材を詰めた買い物袋を両手に提げて、苦労しいしい自室に入る。真冬の外気と荷物の重さで指はすっかりこわばっていた。玄関の開錠に二度も失敗した。鍵がつめたいせいだ。この季節の金属は氷よりもつめたく感じる。
せまい台所の床にどっこらせ、と荷物を置いて、冷えきった居間に入る。電話の留守録の釦が赤く点滅していた。
どれどれ、再生するか。かじかんで白くなった指をのばす。
しかしこわばった指は彼女の意図とちがう動きをした。指は釦を連打した。
しまった。
ぴーーーーー。「録音が消去されました」
あああ、やってしまった。がっくり肩を落とす。
しかしものの数秒で立ち直った。消してしまったものはしかたがない。ほんとうにだいじな用件ならば、相手はもういちど連絡してくるだろう。待っていればいい。
じぶんでじぶんを説得すると、つめたい両手をこすりあわせた。それから暗くなりかけた室内をみわたし、壁ぎわによって照明と暖房の電源釦を押した。