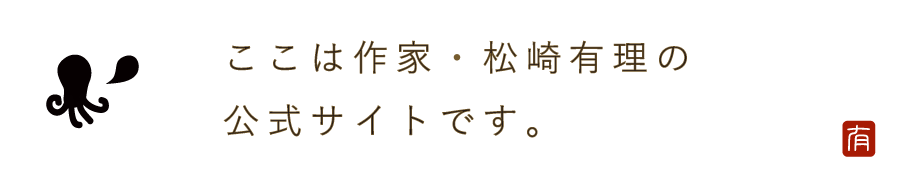作成日:2017/09/18 最終更新日:2017/09/21 かいたひと:松崎有理
職安。
いうまでもないが、職業安全保障部局のことだ。
その職安の、求人情報検索機の前にシーノが座っていた。きょうは雇い主から休みをもらった。そこで朝から、阿多語噛杉通と廣瀬通の交差点にある北の街支局にやってきて、ついたてで仕切られた座席で機械との声のない問答を繰り返していた。
画面に触れる。さいしょの質問が出る。あなたの年齢は。
二十七歳、と入力する。
つぎの質問。性別はかっこ参考かっことじ。
女、と入力。参考、とあるのは、就職における性差別をなくすためだという建前はもちろん知っていた。もちろん建前でしかないことも。
最終学歴および所持する資格は。
大学院博士後期課程修了。博士かっこ理学かっことじ。専門は、希少生物ホラホラ属の分類。
希望の職種は。
研究職。
慣れきった指づかいでそこまで入力して、検索開始釦に触れる。画面は暗い青に変わり、おまちください、という白い文字が中央に浮かんだ。画面の右隅では目がむやみと大きい桃色のいるかが水しぶきをあげて踊りはじめた。
戯画化された、しかしたいしてかわいらしくもない踊るいるかをながめながら、シーノはこの検索機の構成を考えたひとについて思いをはせた。そうとう疲れていたのだろう。なんにちも家に帰れず、職場の床に寝袋を敷いてかりそめの睡眠をとる。風呂に入れないから深夜こっそり給湯室で髪を洗う。抜けた髪が排水口につまってお局的女性社員に文句をいわれる。昼食は砂のような社食、夕食は砂利のような即席めん。上司はこれといった指示も出さずにただ早くしあげろ、と繰り返すだけ。それでつい、待機画面にこんなろくでもない、やくざな、へんな顔でへんな色をしたいるかを踊らせてしまった。そうしてひそかに溜飲をさげたにちがいない。
名前も顔も知らない情報技術者にたいし、シーノは同情の涙をながす。
ああ、しかし。どんなにひどい待遇でも、どんなに理不尽な上司がいても、希望の職種につければまだましだ。
じぶんよりは。
いまの仕事。あんなの、ぐうぜんみつけた腰かけだ。長く勤めるつもりはない。らくちんだし報酬も悪くないが、それでも。
画面が明るく光る。架空の情報技術者の不幸を象徴する桃色のいるかは消えて、検索結果が表示される。シーノは思考の世界から舞い戻って検索機に顔をちかづける。
条件に一致する求人は、零件。
深くふかくため息をついた。いつきても、何度やっても同じ。やっぱりじぶんの専門を活かせるような職なんてないんだ。
じぶんの好きな、じぶんに向いた、やりがいのある仕事は、存在しない。
深くふかく絶望して、シーノは検索機の椅子から立った。肩を落として振り返ったとたん、室内を横切る若い男と目が合った。
「あっ、シーノさん。いらっしゃい」
シーノ担当の職安相談員は、上品な色白の顔にひとあたりのよい微笑を浮かべた。ふちなしめがねの奥の目はちゃんと笑っていた。ほんのすこし逆立てた髪は親しみすら感じさせる。だが。
役人だ。
うろたえぎみに会釈を返す。こんなとき、いやどんなときでも、とっさにことばはでてこない。
相談員はシーノの背後の検索画面をちらとみて、微笑をたたえたままでいった。「まだあきらめてないんですね、研究職」
うなずいた。すくなくとも求職については、この男にかくしごとはできない。
ほかの検索機をつかっている求職者たちに配慮してか、相談員は一歩シーノにちかづいて声を低くした。「ぼくは、あなたに向いていると思いますけどね。いまの仕事」
苦笑して、首をすこしかたむけた。向いてるんだろうか。ほんとに。
嘘道の家元秘書なんて、へんな仕事が。
「木と話すにゃあ」三本脚の脚立にのぼったトクさんは、手にした植木ばさみでよく茂った常緑樹の枝をいっぽん、切り落とした。ぱっちん、という潔い音が蛇足軒の庭にひびきわたった。「ことばは、いらにゃあです」すっぱりななめになった切り口に目をちかづけ、日焼けした顔に満足そうな笑い皺をつくってなんどもうなずいた。
かなかなかなかなかなかな。ちいさな庭のどこかで、生き残りの蝉が夏の終わりを悲しげに告げていた。かなかなかなかな。
シーノは出入りの庭師の仕事ぶりを横目でみながら、池のふちにしゃがんで金魚に餌をやっていた。いちゃぽん、と彼女が命名した鯉ほどもある巨大らんちゅうは、ぶかりと泡をつくって水面ちかくまであがってきては、投げこまれたたこやきを大きな口でひとのみにしていた。
こいつ、どこまで大きくなるのかな。
金魚めがけて、たこやきを落とす。なんでもいいから丸いもの与えてね、というのは雇い主の蛇足軒からの指示だった。たしかにこの金魚は丸いものならなんでも食べた。しかも大量に。
いまも、出勤とちゅうにシーノが買い求めてきたひと舟ぶんのみそ味たこやきをすべて平らげてしまいそうないきおいだ。
この調子なら、とシーノは考える。いちゃぽんはどんどん成長して、より大きな丸い食べ物が必要になるだろう。ゆでたまご。桃。おにぎり。小玉すいか。中玉すいか。大玉すいか。
脳裏に鯨のごとく巨大化したいちゃぽんがあらわれ、巨大な丸い口をあけて食料を求める。しかも人語をしゃべる。鐘を割りそうな低い声で、なにかくれ、もっとくれ。
ひゃああ、大きくなったなあ。想像のなかのシーノは意外と冷静で、ちいさな池から立ちあがる超巨大らんちゅうをむしろ誇らしげにながめている。
ぱっちん。トクさんの植木ばさみの音がひびく。かなかなかなかなかな。蝉が鳴く。
「なんとなく、わかるんだにゃあ」庭師は訥弁というほどではないが、口調はきわめてゆっくりで、作業の手つきもまたゆっくりだ。「木をじっくりみてるとね。どこ切ってほしいのか、って」そういいながら、いま作業している名前のよくわからない常緑樹の枝ぶりをすかしてみて、枝と枝のあいだに手を差し入れ、またはさみでぱっちん、と細い枝を落とす。
動作は遅いけれど、ひじょうに的確。
造園になどまったく興味のないシーノだが、蛇足軒の庭がよく手入れされ美しく維持されていることくらいは理解できた。雇い主がみずからやっているとは思えないので職人を定期的に呼んでいるのだろうと推測していた。
それがトクさんだった。
一分刈りにした頭に手ぬぐいではちまき、屋号を白く染めぬいた藍色の腹掛け、軍手に地下足袋。庭師ときいてさいしょに思い浮かぶ姿そのままだ。顔はよく日焼けして松脂みたいな色つやで、一面からすが歩いたあとのような皺でいっぱいだ。髪は短いから色がわかりにくいけど、おそらく半白。だから六十歳前後といったところだろう。庭の持ち主とちがって年齢の推定がしやすい。
かなかなかなかなかなかな。蝉がかぼそい声で鳴く。
トクさんはうううん、とうなってから脚立のうえですこし体をそらし、いま手入れしている常緑樹ぜんたいのかたちをみた。それから満足げにうなずいて植木ばさみを腰に戻すと、かわりにそれまで腰に吊っていたちいさな帚をとって、木の表面をやさしく叩くようにして切り落とした枝を払った。そして。
「ちょっと早いけど、昼飯にするかにゃあ」と、いって脚立から降りてきた。
シーノは池のふちから空をみあげた。夏の終わりの太陽はもうすぐ南中しようとしていた。
三十三代目蛇足軒こと第二百二十五代百歩七嘘派家元はまだ起きてこない。
毎朝の出勤直後にむりやり起こすことはとっくにやめていた。だいいち探すのがめんどうだ。雇い主は寝相が悪い。とても悪い。ものすごく悪い。夢遊病といっていいほどだ。寝室にしている南の小部屋の布団でみつかったことは、ここで働きはじめてすでに数か月になるが、いちどだってない。物入れ、しかも上の段。廊下の隅。廊下のまんなか。玄関の三和土。台所の床。台所の床下収納。風呂場。縁側。縁の下。庭のつくばいのそばで丸くなっていたことすら二度もあった。主と同じ名前の蛇足軒という建物は平屋のちいさな家で、塀で囲まれた庭もごく狭いのに、捜索は毎朝難航した。ようやくみつけたときの心理的打撃も大きかった。
なんでまた、こんなところに。
そういう脱力感は確実に彼女を疲弊させた。だからほどなく、寝ている雇い主は放置しておくことになった。そもそも、まいにち通ってくる熱心な弟子もいないから、家元がそう早起きする意味はない。それに家元秘書の仕事として命じられているわけでもなかった。
いちばんだいじな仕事は。
シーノはふたたび池をみた。緑色がかった水のなかで、鯉ほどに育ったらんちゅうがぷかりと大きな泡を吐いた。
この金魚に餌をやること。蛇足軒はさいしょにそう、はっきりいった。
しかし、なぜ。
ゆうぜんと泳ぐいちゃぽんをながめながら首をかしげる。ここにはまだまだ、わからないことがたくさんあった。この金魚をだいじにする理由も。それに嘘道の家元が、どうして、あんな。
「ここ、借りますにゃあ」
目をあげると、小風呂敷の包みを手にしたトクさんが縁側に腰を下ろしたところだった。
庭師は嬉しげに両手をあわせ、いただきます、といった。包みを解く。木を楕円のかたちに曲げてつくった弁当箱があらわれた。
たこやきがふたつ残った経木を手に、シーノも縁側まで行ってトクさんのとなりに座った。
軍手を脱いだ手が弁当のふたを開く。
シーノは思わず息をのんだ。
弁当のなかはまるで絵画だった。いや、おもちゃ箱だ。遊園地かもしれない。
中央に薄焼き卵でつつまれたごはんがあって、表面にはあざやかな赤い調味料でトクさんの名前が描かれていた。まわりには丸く抜いた橙や緑や黄色の野菜。甘酢餡の肉だんご。つやつやした朱色の腸詰。
きれいだなあ。いや、かわいいなあ。
弁当をみつめつつ、今朝これをつくったトクさんの妻を脳裏に思い描いてみる。歳は、トクさんとおなじくらい。はんぶん白くなったまっすぐな髪をうなじのすぐ上できれいに丸くまとめている。洗いたての前掛けをつけて、皺がめだつようになった手で長年つれそった夫の弁当をつくる。彼女は色彩感覚にすぐれているので毎回実験的なおかずの配置を考え出す。しかし、味付けはうすめでしっかりだしが利いていて、うまい。みためが楽しく美しく、食べてもおいしいものを、と心がけている。長年の経験がそれを成功させている。
しあわせだな、トクさん。
シーノは手元の経木に目を落とした。このたこやきは彼女の部屋がある架須賀町通ぞいで買った。いせよし、という仕出し弁当屋がさいきん事業展開をしてはじめた持ち帰り弁当店なのだが、なぜかたこやきも売っていた。いせよしの弁当がどれほどまずいかは、大学の研究室が昼食の契約をしていたから知り抜いている。しかし持ち帰り弁当のほうは二代目が経営しているときくし、なにしろ大食らいの金魚のためにどうしても丸い食べ物が必要だった。そこでつい、自宅ちかくのこの店に飛びこんで買ってしまった。もちろん領収書も忘れなかった。
経木のうえのたこやきをあらためてながめる。みためはふつう。きれいに丸くてすこし焼き目がついて、かすかにみその香りがする。
「ああ、うめえ」となりのトクさんは愛妻弁当に舌鼓をうっている。
きゅう。腹が鳴った。そうだ、食べてみようかな、これ。
と、思ったとたん。「シーノさんや。ひとつ、もらってもいいかにゃあ」
いいとも悪いとも返さないうちに、トクさんの松脂色の右手がさっと伸びて、経木からたこやきをひとつ、さらっていった。
「うん。こいつぁ、うめえ」ゆっくり咀嚼してのみこんでから、初老の庭師は松脂色の顔に満足そうな微笑を浮かべた。
そうか、おいしいんだ。よかった。
だけど他人に毒味をさせたみたいで心苦しいな。
でも、まあ、かってに持っていったんだから。
心中のひとり問答を済ませて安心し、さいごにひとつ残ったたこやきを口に運んだ。ひとくちで食べるにはちょっと大きい。はんぶん、かじりとる。奥歯で噛みしめる。
なんだこりゃ。
吐き出したいのを必死でこらえ、涙目でのみくだした。みそ味。しかし、甘い。ほのかに酸味も。いったいなぜ。
はんぶんになったたこやきをながめた。小麦粉の生地の中央におさまっているのは、おきまりの蛸の切れ端ではなかった。
たこやきをためつすがめつし、しまいに指先で切り口をなでてから舌にあてた。そうだ、これは。
ぶどう。しかも超大粒の。
かなかなかなかなかなかな。庭のどこかで蝉が鳴く。
そういえばあの店。新商品秋の味覚たこやき、って貼紙があったっけ。どういう意味かなんて考えもしなかった。
以前のいやな記憶もよみがえってきた。いせよしの仕出し弁当。あそこの十八番は、たしか。
みそ味果物てんぷら。
たこやきの残りを舟にもどして肩を落とした。いせよしの精神は二代目にもしっかり受け継がれていたようだ。期待したのがまちがいだったか。
シーノが後悔の涙をはらはらと経木に落としているあいだにも、トクさんはうまい、うまいを連発しながらしあわせそうに弁当を食べつづけていた。
かなかなかな、と鳴いていた蝉の声がぴたっとやんだ。
「むううう。んんんんんん」よく知った声がきこえてくる。なぜか、上空から。
指先で目尻をぬぐって顔をあげる。すると。
軒からだらん、と片腕がさがった。みるまに拳はにぎられて、んんんんん、というよく知った声がまた、きこえた。
シーノは立ちあがった。なんでまた、こんなところに。
寝乱れた黒い髪がみえた。動いた。
嘘道家元、第三十三代蛇足軒四十七歳、でも見た目は年齢不詳、は頭をふって、庭に立ちつくす新米秘書を藍色の屋根瓦の端からみおろした。「やあ。おはよう」
もう昼だぞ、とシーノは内心でつっこむ。
「ああ、家元。おはようございます」縁側のトクさんは弁当を食べる手をとめて顔をあげ、玄関先でするかのように自然にあいさつをした。
「あ。きょうはトクさんの日か」蛇足軒も自然に返して片手で浴衣の襟をなおし、絶食した喜劇俳優みたいな顔に笑みをたたえる。
「待ってくださいにゃあ。いま脚立もってくるで」トクさんもひきつづき自然にそういって、食べかけの弁当を縁側に置いて腰をあげた。
シーノは深くふかくため息をついた。ああ、これがいまのじぶんの日常だ。
研究職とはほど遠い。
「ことしの夏も終わりですね」背中をむけて居間に座っているのはシーノ担当の職安相談員だった。かるく逆立てた髪のせいで、うしろすがたでもひとめでわかる。
かなかなかなかなかな。庭に面した大きな硝子戸は開け放たれて、かぼそい蝉の声がきこえてくる。きのうにつづいて庭に入っているトクさんの植木ばさみの音も合いの手のようにときおりひびく。ぱっちん。
「そのようですね。さびしいことです」蛇足軒は芥子色の着流し姿で、一枚板の長卓をはさんで相談員と差しむかいに座り、愛用のきせるに刻みたばこをまるめてつめていた。燐寸で火をつけ、しあわせそうに目をほそめて、吸う。白い煙を吐く。
昼食にするからなんか買ってきて。雇い主にそう命じられ、指定された洋菓子店あまんざ、までおつかいに行って帰ってくると、居間ではこんな光景がくりひろげられていた。
シーノをみとめた蛇足軒はきせるを口から離しておかえり、という。「菓子、切ってきて。お客さんにも。それと珈琲ね。きみのぶんも忘れずに」
相談員はふりかえってシーノに会釈し、ほほえんだ。役人らしからぬさわやかな笑みだ。
だまされるか。シーノはちょっとむっとする。役人め。いや、役人たちめ。
じぶんが研究職につけず、こんなところで秘書という名の雑用係をやっているのは、あいつらのせいだ。あいつらの無能な同類が、博士増員十万人計画なんてむちゃな法律を制定し施行したせいなんだ。
おかげで、ホラホラ属の分類という地味な専門を選んだじぶんには就職先など残されてはいなかった。
そんな不満を脳内でぶちまけながら、せまく短い廊下を抜けて台所につく。抱えてきた菓子箱を開ける。あらわれたのは、蜜をかけつやを出した翡翠のごとき緑色のぶどうをあしらった一台の焼き菓子だった。
ぶどうって、こんなふうにつかうのが本当だろう。老舗菓子屋の秋の新作をほれぼれとながめ、それからきのうのたこやき事件を苦々しく思いだした。もうあの店では買わないぞぜったい。弁当も、弁当以外も。
かなかなかなかな。ぱっちん。庭からの音は、台所にいてもかすかにきこえる。
そういえばトクさん。あのたこやきおいしい、っていってたよな。
しかし、そこで思考をやめて、長く刃のうすい包丁を手にとった。さあ、仕事仕事。腰かけとはいえけっこうな給金をいただいているのだから、まじめにやらねば。
きれいに八等分した焼き菓子と淹れたての珈琲を盆に載せて居間に戻ると、どうやらふたりの話し合いはほぼ終わったようだった。
「と、いう特殊求職者なんです」若い相談員は柔和な微笑を色白の顔に浮かべた。「また、よろしくおねがいしますね」
蛇足軒はシーノにたいし、ありがとありがと、きみもここにいなさい、といってからこう質問した。「明日くるのかな、そのひと」
菓子と珈琲をならべるシーノに、相談員は礼をいい、それから家元の質問にこたえた。「天気がものすごく悪ければ」