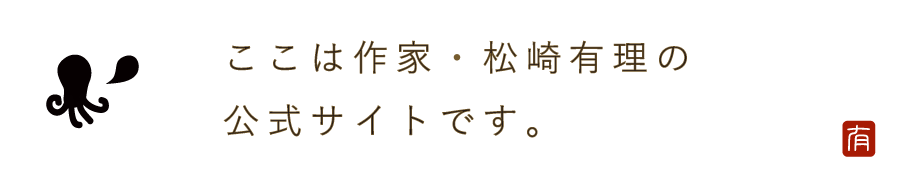作成日:2017/09/02 最終更新日:2017/09/02 かいたひと:松崎有理
人間のやることは凶暴すぎる。 宮崎駿「空のいけにえ」(サン=テグジュペリ『人間の土地』、新潮文庫より)
***
どこにも怪我はないようだった。
不幸中のさいわい、と定型句をつぶやいて、少年は空をみあげた。嫌味なくらい徹底的に晴れわたっていて、雲の存在など忘れてしまったかのようである。太陽はほぼ空の頂点に達しており、残酷なほど強烈に地表をあぶりつづけている。火にかけた鍋の底にいるみたいだった。いまは十二月、この大陸は真夏だ。
はたしてこれは幸運なのか不運なのか。
少年は金色の頭をめぐらせてまわりをみた。髪は煤と埃にまみれ、汗で額に貼りついて不快だった。周囲では小型双発機の残骸がいまだ黒い煙を立てて、鉄のこげるにおいを放っていた。座りこんだ尻の下は強い日差しでからからに灼かれた黄色の砂。その砂は、うねりくねってゆるい丘をつくりながら視線のはるか先までつづいている。立ちのぼる熱気のために風景はゆがんでいる。とげだらけのいじけた植物がごくまばらにしがみついている以外、生命の気配はない。北方のやわらかな緑の景色に慣れた先祖たちが赤道を越えてこの地に入植してきたとき、まるで異星のようだと感じたのも無理のない話だった。
だがこれが現実だ。
もっと遠くをみようと少年は身をよじった。
「いってえな。引っぱんなよ」
すぐさま、喉をつぶした牡牛のような声が左どなりから飛んできた。金髪の少年はおざなりに謝って、姿勢をもとに戻した。手首の鎖がじゃらりと鳴った。片手ではない。両方である。
「いいか。忘れんなよ、もしこの手錠がはずれたら」左どなりの少年も両手についた鎖をうるさく鳴らした。年齢的には少年のはずだが、その体格は成熟した重量あげ選手のようである。胸は分厚く、体毛が濃い。腋臭もひどく、金髪の少年は彼とつなぎあわされてからずっとその悪臭に悩まされてきた。護送機が墜落し真昼の砂漠に放り出されたあと、においはますますきつくなったようだ。「はずれたら。まっさきにおまえを襲う」
「はいはい。わかったわかった」金髪の少年は相手の台詞を聞き流した。左どなりは自身の犯行を機内で自慢げに吹聴するようなやつだった。これまでの犠牲者は男が二十八人、女が七十一人。だからもうひとり犯せば記念すべき百人斬りなのだそうだ。
自分にとって主たる不運のひとつは、こいつのとなりになったことだな。金髪の少年は連続強姦魔の品性のないひしゃげた鼻をみつめた。その鼻の頭には汗の粒がひしめいていた。すすけた顎にはひげが伸びはじめている。
強姦なんて最低クラスの犯罪だ。殺しのほうがまだましに思える。
「はずれたら。はずれたら」強姦魔はいらいらと鎖を振り、両手を握ったり開いたりした。鋼鉄製のがんじょうな手錠は宗主国警察の特製であり、脱出技で名声を博した世界的奇術師ですら解錠に一時間を要したといういわくつきである。ふつうの人間の手に負えるものではない。「おおい。だれか、こいつをはずしてくれええええ」
彼の牡牛のような声が真夏の空に響く。
「だれもはずしちゃくれないよお」金髪の少年の右どなりがいった。まだ変声していないように高く細く、しかも鼻声だ。髪は赤く、頬にはそばかすが散っている。「さっき、みんなで確認したじゃないか。ぼくら以外は全員死んだ。護送官たちはだれも手錠の鍵を持っていない。鍵のかわりになるような尖ったものはいっさい積んでいない」
この気弱そうなやつが三十七人を殺して何週間も新聞各紙を賑わせた張本人とはなあ。金髪の少年はあらためて右どなりをながめた。あれはまるでいじめられっ子タイプだ。
「だれか、手錠をはずすスキルを持ってるやつはいないのか」そういったのは、強姦魔の左どなりにつながれた少年だった。背が高く、黒髪を秀でた額のまんなかでゆるく分けている。瞳は空色で鼻は高く口元は締まっている。彼の雰囲気はほかの少年たちと一線を画していた。そのちがいは、みなとそろいの青いデニム地のつなぎを着せられていてもはっきりわかる。まるで寄宿学校の優等生をひとり混ぜこんだようなのである。それもそのはず、彼がここにいるのは冤罪のためということであった。彼は機内でひたすら自分の無実を訴えつづけていたが、護送官たちはいっさい耳を貸さなかった。「きみらはみんな凶悪犯罪者なんだろう。つまり、若くして第一級の極悪人たち。鍵を開けるなんて朝飯前、ってやつがひとりくらいいそうなものだけど」
「いるよ」金髪の少年はため息まじりにいった。「だが、死んだ。いちばん右端の死体、それだ」
年端のいかぬ少年ながらおそるべき解錠の技術を持つ大泥棒は、墜落のショックで頸椎を折って即死しており、いまは殺人者の右手にだらりとつながっていた。
しみじみ不運だ、と金髪の少年は思う。あの天才無免許鍵師が生きてさえいれば、このいまいましい手錠のつらなりから自由になれたのに。なにより腋臭の強姦魔から。
「叩き壊すしかねえな」いちばん左端、ひとりだけ片手が自由な少年がいった。ひどく痩せて顔が青白い。罪状は麻薬取引だった。自宅で極秘に大麻を栽培していたという。顔色が悪いのは陽にあたらない生活のためだろう。「そこらに機体の破片がいっぱいころがってんだろ。手ごろなのを拾って、試してみたら」
「ひひひひひひ」虫のような声で笑ったのは、麻薬取引と冤罪のあいだにはさまれた幼児のように小柄な少年である。彼だけがめがねをかけている。遠視用らしく青い両目がレンズで拡大されていた。自分の住む村さえ焼き払ったという放火魔だが、これまでいちども知性の感じられることばを発していない。「ひ。ひひ。ひひひひひひひ」
「手錠はずすのもだいじだけどよお」殺人犯が高い声をあげた。「おれ、逃げたいんだよう。だって捜索隊がきて、またつかまって刑務所についたら、おれ確実に死刑なんだよう。いま、すぐここから逃げたいよう」
「ぼくも逃げたい」冤罪はこの場に似合わぬ落ちついた、しっかりした声でいった。「ぼくも、捜索隊につかまればそのあとは死刑だ。なにも悪いことをしていないのに死ぬなんてぜったいにいやだ。きみらとはちがう」
「おれも一票」強姦魔がいう。「おれはたぶん、合計数万年の懲役刑。この先一生、薄くてくさい粥だけすすって強制労働だなんて。やってられっかよ」
「待て。状況を考えろ」金髪の少年は強くさえぎった。「飛行機は墜落のさい予定のルートをはずれた。つまりおれたちは現在位置を知らない。ひとが住む地域まで何千マイルあるかわからないんだ。それに、いまは真夏だ。ろくな装備もなく徒歩で砂漠を横断するなんて自殺行為だぞ。水がなければ人間は三日で死ぬ。ここにとどまって救助を待つのが最善だ。砂漠はみはらしがいいから事故機はすぐに発見されるだろう」
「さあすが。論理的だねえ」麻薬取引は組んだ膝を空いたほうの手で叩いた。「おれも、とどまるほうに一票。天才詐欺師さまにしたがったほうがいい」
詐欺師と呼ばれて、金髪の少年は胸のうちに熱い誇りの感情をおぼえた。詐欺師とは犯罪界の貴族。殺人や強盗などの卑しい肉体労働にはけっして手を染めない。つねに頭を使ってスマートに大金を稼ぐ。カモからむしりとるのではなく、向こうから金を差し出したくなるようしむけるのである。
裕福なカモにとりいるためには広範な知識と教養が必要だから、詐欺師は若いうちから学校に通わずともせっせと本を読む。またカモ自身からも学ぶ。主たるカモは成功した実業家や財産家で、自分の経験と知識をしばしば自慢げに披露してくれるものだ。
詐欺師はカモの金で優雅に、堂々と暮らす。新たなカモと知りあうため、一流ホテルに滞在しファーストクラスで移動する。名士とされることさえある。ほかの犯罪者のように逃げ隠れしない。逃げねばならないのは根回しが足りないせいで、それでは詐欺師失格なのである。
だがいかに天才的な信用詐欺師であっても、運に見放されることはあるものだ。だからいまここにこうして座っている。炎天下の砂漠で、つぶれた囚人護送機のそばで、ほかの犯罪少年たちと手錠でつなぎあわされて。
詰む一歩手前だ。
「おまえらは死刑じゃないから、いいだろうけどよう」赤毛の殺人者がすねたような声を出した。
「刑期も長くなさそうだしな」強姦魔は分厚い唇をゆがめていた。その端には細かい泡がたまっている。「それにどうせ、外の仲間が金払って出してくれんだろ」
指摘はあたっていたが、詐欺師はだまっていることにした。どんな返答をしても相手を激昂させるだけだ。
「おい、火つけ。おまえはどう思う」痩身の麻薬取引が右手の鎖を引っぱる。だが小柄な放火魔は、ひひひひひ、と笑うだけでまともな返事をしない。
「そいつは棄権だな」冤罪がいった。「じゃ、多数決の結果。三対二で、いますぐ逃亡に決定だ。ぐずぐずしていると捜索隊がきてしまう」
「待てよ」詐欺師はまたも強くさえぎった。「生死にかかわる判断だぞ。多数決でいいのか」
「ほかにどんな方法がある」冤罪が優等生じみた視線を投げてきた。「多数決による決定はもっとも公平で、民主的で、みなが納得できる手段じゃないか」
「そうだ、そうだ」強姦魔が賛意を示す。
投票は絶対的に正しい意志決定手段ではないことを説いた社会数学の理論は魅力的であったが、こんなとき使うには複雑すぎた。「おれたちは手錠でつながれている。一蓮托生なんだ、全員が死ぬかもしれない」こっちのほうがシンプルで説得力がある。
「逆に。全員が生き残れるかもしれない」冤罪が返す。「もし逃げなかったら、ぼくを含めてふたりは確実に死ぬんだ」
「不運なきみの立場には同情する。きみのばあい、たんに巻きこまれたにすぎないんだから」対立者の立場にいったん理解を寄せるのは説得のための有用な技術である。「でも。つかまったって、すぐさま死刑になるわけじゃない。控訴できるし、獄中から無罪を訴えればきっと新聞社が」
「あああ。はやくしないと追っ手がきちまうよう」殺人者が高い声をあげた。
「食料と水を持っていけばいいんだろ」冤罪は空色の両目で詐欺師をみつめた。「それに、砂漠はけっして不毛の大地じゃない」と、いじけた植物の茂みを指した。「土着の生物がいるし、先住民だってここでりっぱに暮らしている。ぼくらがたちまち乾ききって死んでしまうようないいかたはやめてくれ」
「そうだ、そうだ」強姦魔が和する。
「たしかに、それは嘘じゃない」詐欺師は唇を噛んだ。「だが、甘い。認識が甘すぎる。みんな砂漠のほんとうのおそろしさを知らないんだ」
かくいう詐欺師も、カモのひとりから若かりし日の内陸部探検の体験談をきいただけなのだが。
すると冤罪は。「つかまるのなら、死を選ぶ」