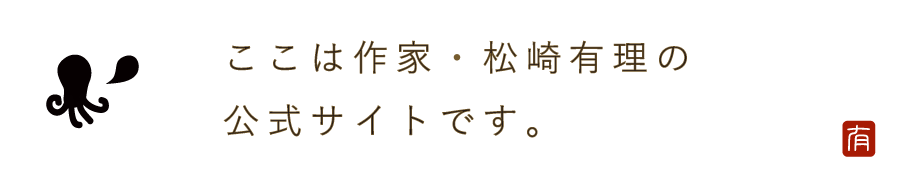作成日:2017/09/18 最終更新日:2017/09/20 かいたひと:松崎有理
二十七歳、女、無職。
じぶんを冷静に評価分類するとシーノはため息がでてしまう。
もちろん無職なんかじゃないといいはることもできる。じぶんはこの春、蛸足大学理学研究科生物分類学分野で博士号をとり、いまはそこで研究員をしているのだと。
だが、と彼女はまたため息をつく。研究員とは名ばかりだ。だって無給なのだから。
実質、無職と変わらない。
ああ無職。いやなひびきだ。世間さまから石をなげられ、うしろ指を差されるにじゅうぶんな称号だ。きちんと職をもち納税しているひとたちからの架空の怒号がきこえる。社会のお荷物。無為徒食。ごくつぶし。税金泥棒。
あああ。
涙が流れそうになったので、あわてて無職を就職浪人ということばで置き換えてみる。刀のかわりに博士号取得免状をまるめて腰に差し、研究職をもとめて各地をさすらう。しかしあわれ、世間の風はつめたい。職はいつまでもみつからず、博士号もち浪人のさすらいの旅はつづく。
やっぱりみじめじゃないか。
きりがないので頭をつよく振って妄想を追い払った。学生時代からひきつづき住んでいるちいさな貸間で、彼女は黒い上下に着替える。黒いかばんを持つ。なかには必要事項を記入ずみの履歴書が入っている。せまい玄関で黒い靴をはく。服にしわがないか、糸くずがついていないかを確認する。女のひとりぐらしを守るにはなんともたよりない薄い扉を開けて、あちこち塗装のはげた鉄の手すりの階段を降り、通勤時間帯がおわったばかりの架須賀町通に出る。雨期に入る直前の北の街はきょうもくやしいくらいさわやかな天気だ。朝の日差しが目を射る。涙がにじむ。
シーノがむかうのは大学ではない。
職安だ。
「やってみたい職種は、きまりましたか」
いつもの相談員がついたてで両側を仕切られた机をはさんで差しむかいに座っていた。彼の歳はシーノとあまり変わらないだろう。ふちなしのめがねの型は流行のもので、短めの髪は嫌みにならないていどに逆立てている。上衣はあくまで白い。清潔感があり、かつあまり役人らしくないやわらかな印象だ。
シーノは膝にかかえたかばんの持ち手をぎゅっとにぎり、質問にたいしてなにもいわずに首だけ振った。
「そうですか」相談員はひとあたりのよい微笑を浮かべる。初回の面談で、彼はシーノの訥弁ぶりをほぼ瞬時に見抜き、以後は彼女があまりしゃべらずにすむよう進めてくれていた。いつ面接することになってもいいよう、つねに黒い上下を着用し履歴書を持ち歩くことを提案したのも彼だ。若いが有能であることはたしかだろう。「あせる必要はありません。職業をえらぶのはだいじな問題です、時間をかけて考えていきましょう」
いっしょに、ね。そのためにわたしたち職安相談員がいるのです。
うなずいて、右側のついたての貼紙に目をやる。貼紙はこううたう。職安憲章。懇切、ていねい、秘密厳守。
だが、あせらねばならないのはわかっていた。二十七歳にもなってなんの職歴もなく、持っている資格免許のたぐいは博士号という、およそ一般企業に縁のないもののみ。しかも女。そしてこの訥弁。
不利な条件がそろいすぎている。
「前回やっていただいた適性検査ですけど」相談員は机の下からなんまいか紙をとりだし、目の前に広げる。
性格診断と職業興味診断を組み合わせた検査だった。結果。社会性と協調性は最低。論理性と審美性が突出。診断。孤独な仕事むき。具体的には芸術家、研究者など。
とてもよくあたっている、とシーノは思う。
「やっぱり、研究職志望なんですね」若い相談員は彼女の表情から心のなかをよむかのように話をすすめる。なぜこんな魔法のようなことができるのか。
「しかし。前回も申しあげましたが、企業さまが研究職として新卒採用するのは修士課程卒業見込者です。正直なところ、企業さまの採用担当者さまはみな、博士号取得者は専門性が高すぎて、とおっしゃいます」
専門性が高すぎる。つまり、つかえないという意味だ。
そういわれてもしかたがない。なにせ彼女の専門は、ホラホラ属というきわめてめずらしい生物の分類と記載なのだから。これほど特殊な専門性を企業の研究所でどうやって活かせるのか。
相手はシーノの顔をのぞきこむ。「大学での職は、どうしてもみつからないんでしょうか」
悲しげに眉をさげてうなずく。有給研究員の地位に空きがあってぶじすべりこめるようなら、いま彼女はこんなところに座ってはいない。
研究職以外の職種をおすすめしますよ。相談員はきょうもこの助言でしめくくった。
十年前のことだ。
政府は例によって急に、なんの脈絡もなく、科学技術力の底上げが必要だと痛感した。そして例によって短絡的に、博士号取得者を大幅に増やせばよいと結論した。
博士増員十万人計画。
そんなむちゃな法律があっさり制定された。粗製濫造された博士たちに研究者としての就職先があるのか、というだいじなことはまったく考慮されずに。そもそも、世界金融危機に端を発した第二次就職氷河期の終結がみえない時期でもあったのに。そして十年たったいまも、若者の就職難の状況は変わっていない。
シーノもこの法律の犠牲者だった。
だから役人はきらいだ。シーノは職安相談員の柔和な微笑をながめてため息をつく。彼個人に罪はないが、それでもきらいだ。
かれらには職があるじゃないか。だからそんなふうに笑っていられるんだ。
「またきてくださいね。おまちしております」シーノを見送る相談員はふかぶかと頭をさげる。たしかに懇切ていねいだ。だがその態度は、定年まで保障されたたしかな身分があるという余裕に裏打ちされている。
余裕なんかない。わたし余裕なんてない。
ああ役人だいきらいだ。こんな苦労をするのもみんな役人たちのせいなんだ。
職安の建物を出る。まだ正午にもなっていなかった。初夏の蒼羽通はけやきの緑が皮肉なくらいまぶしく光っている。適度に湿気をふくんだ空気のにおいは涙がにじむほどすがすがしい。シーノはいつものように徒歩で自室まで帰る。交通費を節約したいからだ。
黒い靴のかかとをかつかつ鳴らしながら蒼羽通の広い舗道をあるく。じぶんが無能な粗製濫造博士たちの一員だとは思いたくない。しかしこの春、一部の同期たちのように各地の大学や研究所へ赴任できず、いまこうして職安通いをしている現実が、じぶんの研究者としての才能のなさを証明している。いや才覚というべきか。研究者には研究者なりの協調性や社会性が要求される。とくに所属研究室の教官たちと親密になっておくのは重要だ。博士号取得後の就職先を探し、紹介状を書いてくれるのはかれらなのだから。
じぶんは配慮に欠けていた。準備を怠った。
しかし後悔しても遅い。
立ちどまり、通りに面した百貨店の巨大な硝子扉に映るじぶんの姿をみた。身をつつむ黒い上下はいかにも板についていなかった。学生時代、こんな服を着るのは学会発表のときくらいだった。染めていない髪はあごの下くらいの長さ、化粧気はない。化粧はじぶんが別人になってしまうようできらいだった。そもそも理学部に通う数少ない女の子たちはみな、化粧などしていなかった。
いまじぶんは悲しげな目をしている。置き去りにされた子犬のような。だめだ、こんな顔では就職活動なんてうまくいくわけがない。
頭をひとつ振る。勢いだけはよく、ふたたび舗道をあるきだす。かつんかつんかつんかつん。靴のかかとが鳴る。こんな靴だってこれまでめったに履かなかった。
思えば多忙な学生であり大学院生だった。かかとのある靴を履いて親しい男の子と腕を組み蒼羽通や壱番丁をあるく、なんていちどたりともしたことがない。
あのころは忙しかったからさびしいとは思わなかった。でもいまは。
から元気をふりしぼりながら大きな交差点で右折し、似詩公園通を北上する。桜並木のあいだに花見だんごで有名な言語茶屋の赤い屋根がみえたり隠れたりする。毎年春、まだ肌寒い夜に、あのあたりで場所とりをして無邪気に花見をしたことを思い出す。研究にあけくれるまいにちの、ひとときの娯楽だ。そんなに昔のことじゃないのに。
でもあの日々は戻ってこない。だってわたしもう学生じゃない。
じぶんで稼がなくては。
かつんかつんかつんかつん。靴音だけは元気だ。似詩公園ではちいさな子供たちとその母親たちが原色で塗られた遊具をつかって歓声をあげつつ遊んでいる。どこまでも青い空の上の上の上、対流圏と成層圏の境目あたりでは鳶が数羽、ぴいいいいいい、と高く鳴いて円を描いている。いや厳密には円ではなく楕円か。まあなんだっていい。
みなしあわせそうだ、じぶん以外は。
から元気を維持するため顔だけはしっかりあげて舗道をあるきつづける。似詩公園もそのむかいがわの商店や事務所や専門学校の建物も、街路樹のけやきやかえでの一本一本も、すべてみなれた光景だ。この街にはもう九年すんでいる。学部学生時代四年、たすことの、大学院博士課程五年。つかのまの夏と幾月もつづく冬の、九回のくりかえし。
長かったのか短かったのか。
廣瀬通との交差点、そして上善寺通との交差点をすぎる。街の中心部から離れるにしたがい個人の住居の割合が増える。古くからのしずかな住宅街といったおもむきだ。高い塀をめぐらせた品のある邸宅がつぎつぎ視界をとおりすぎていく。
そんな塀のひとつに貼紙があった。
こんなところに貼紙なんて。思わず足をとめた。ちかよってながめる。達筆の毛筆でこう書かれていた。
急募 秘書一名 無口なかた歓迎 委細面談 蛇足軒
蛇足軒とはここの住人の名前、ということは知っていた。苔むしたちいさな門にはこの名が彫りこまれた表札が下がっていたからだ。もっとも本名ではなく号なのだろう。おそらくこの建物の名前でもある。深い藍色の瓦屋根をもつこの平屋の主についてはよく知らなかった。なにかの家元だという話をきいたことがあるだけだ。
家元の秘書か。ちょっとおもしろそうだ。研究職がみつかるまでの臨時の仕事には、いいかもしれない。それに。
無口なかた歓迎。
このひとことに強く惹かれた。わたし無口さならばだれにも負けない。
シーノは塀にそって早足ですすみ、苔むしたちいさな門にたどりついて呼び鈴を押した。
それがすべてのはじまりだった。
「家元制度というのは古代社会から存在してたんだけど、いまから三百年ほど前が爛熟期だった。このころ、それこそあらゆる無形的な技術が家元をなのる対象になった。華道、茶道、香道あたりはよく知られてるよね。ほか書道や俳諧、唄、囲碁将棋、すこし変わったところでは算法なんかがある。数学にいくつも流派があって試合や道場破りなんかやってたんだよ、剣術みたいに。料理も包丁道といって家元化した。さいしょは宮廷料理や儀式用など高級で手間のかかるものだけだったけど、しだいに大衆化してあらゆる料理が家元となり流派をつくったんだ。たとえば『大根料理秘伝ノ巻』や『鰯料理百珍書』なんて秘伝書が実在してた。そのほか、掃除術や洗濯術、はては居眠り術や薮蚊たたき術なんてものまで家元化してたね。もう家元百花繚乱状態。すべてのひとがなんらかの家元、あるいはその弟子、みたいな」
なんてよくしゃべる男だろう。
シーノはつやのある一枚板の長卓をはさんで座る相手をつくづくとながめていた。どうでもいいことをこれほど話しつづけられる男をいままでにみたことがない。理学部にいる男たちはたいてい、シーノほどではないにせよ訥弁ぎみだった。用件だけを筋道だてて話し、よけいなことはいわない。
「まあ、当時はそれだけ平和だったってことだね。なにせ家元世界は趣味道楽の世界だから」そこでようやく蛇足軒ことこの家の主はひと息ついて、卓の隅に手をのばした。たばこ盆があった。黒地になにかきらきらした金色の模様がいちめんに入っている。下部のちいさな引き出しを開け、わたあめかとみまがうほど細くきざまれたたばこをひとつまみとって豆くらいのおおきさにゆるく丸めた。きせるの火皿につめ、燐寸で火をつける。吸い口をくわえて浅く吸い、離してからゆっくり白い煙を吐いた。なんともしあわせそうな表情をしていた。嗜好品かくあれかし、といいたげだ。
喫煙者をみるのもとてもめずらしい経験だった。健康推進法の名のもとに、大学構内はシーノが入学するずっと以前から全面禁煙となっていたし、街なかでも、公共や民間のあらゆる施設、飲食店、各種交通機関、路上でさえも、たばこの煙が徹底排除されてひさしかった。喫煙習慣はいまや絶滅寸前だ。
シーノは無言で相手をながめつづける。芥子色の着流し姿で痩身中背、まっすぐな髪は肩につくくらいの長さ。年齢はよくわからない。白髪はないし目尻の皺は笑い皺のようだ。歳下ということはなさそうだが、いくつ上かはまったく推定不能だ。
容姿はそう悪くないかも。俳優みたい、はほめすぎか。では、喜劇俳優みたいな。それも一週間ほど絶食したあとの。
やっぱりさほどよくもない。
三服吸ったところで彼は灰入れに灰を落とし、きせるをたばこ盆にもどした。「それでね。うちがなんの家元かというと」
そうそうそれがききたかった。ようやく面接らしくなってきたので安心し、卓上に置かれたじぶんの履歴書と蛇足軒の顔とを交互にみた。
だがその安心はすぐに裏切られた。
相手のこたえはこうだった。「嘘術だよ」
え。嘘術。
なにそれ。
「嘘というのは起源が古くてね。おそらく人間が言語を獲得した当初までさかのぼる」
そこまでいって蛇足軒はきゅうにだまった。視線が上をむき、みるまに眼球は白目だけになった。そしていきなり卓につっぷした。額が固い一枚板にあたり、ごん、という音がした。
ええっ。やだ。なに。どうしたの。
失神。いや発作。なにかの病気。
ほら、緊張病症候群ってあるじゃない。あれかもしれない。
あるいは心臓発作。または脳溢血。
救急車救急車きゅうきゅううううしゃ。
シーノは驚きかつ動揺した。どうしよう。このまま彼が急死してしまったら。面接は、就職はちゃらになる。いやそれより、じぶんが殺人者だと疑われないだろうか。
博士号取得済就職浪人、未知の毒を盛って家元を暗殺。
そんな新聞の架空の見出しが頭のなかを野方図にかけめぐる。
だが幸いなことに蛇足軒はすぐ上体を起こし、なにごともなかったようにほほえんで口を開いた。「でね。言語で真実を語ることを発明した人類は、嘘をつくこともあわせて発明したんだよ。ほら神話にもあったでしょ、このへんの由来」
シーノは背中にいやな感じの汗をかいていた。なんだったんだ、いまのは。
それから蛇足軒は嘘つき神マサカの誕生とその運命についての長い長い物語を語った。彼いわくとても有名な話、とのことだったが、あいにくシーノはまったくきいた記憶がなかった。
まあじぶんは真性理系なのだからこの種の話題にうとくてもしかたがない。そう思って面接者の話を神妙にきいた。
マサカ神は植物の種からうまれた。りんごであるともさくらんぼであるともいわれるが、珈琲豆であるという説が有力だ。しかも双子として出生したのだがうまれ落ちた直後に嘘つき勝負をし、勝ったほうが負けたほうを吸収してマサカ神となったのだという。
こうして完全体になったマサカ神は三日で成長し、成人の儀としてふしぎな老婆の試練を受ける。彼女は臓物を切り刻む女、と呼ばれ、右手に血まみれの小刀を持っている。左手には太鼓をたずさえ、それを鳴らしつつじぶんの影と踊る。背中にはおおきな裂け目があってやせこけた金目鯛がのぞいている。金目鯛はときどき、ぴい、と鳴く。老婆は基本的に無口で、ほんだわらの切れ端、とかへんなうわごとしかしゃべらない。口が横にのびているせいで顔が縦より横に長い。じぶんの尻をなめることが、またじぶんの頬で脇腹を打つことができる。もし彼女をみて笑ってしまったら、たちまちとらえられ桶にいれられて小刀で解体され、食われてしまう。だがマサカ神は華麗かつこっけいな嘘で彼女を逆に笑わせ、この試練を突破する。
成人したマサカ神はその縦横無尽な嘘術で世界を混乱に陥れる。嘘の力でたつまきや大地震がおこり洪水が発生し地形すら変わる。
事態を憂慮した神々はマサカ神の力をうばうことを計画する。マサカ神の弱点は異常にたまねぎがすきであることだった。神々が準備した山盛りたまねぎの罠にマサカ神はそれはそれはあっけなくはまる。
神話はマサカ神の二枚の舌が両方とも抜かれ、かわりに黄金の舌を移植されるところで終わっていた。
「と、以上の物語は約二千年前の木版印刷書『南海沿岸嘘伝上陸誌』に記録されてるんだ」
へええ。シーノは歴史にもうとい自覚があるのでひきつづき神妙にきく。
すると相手は片側の頬にへこみをつくって微笑した。「あ。信じた信じた」それから天井をみあげて高い声で笑った。
え。まさかいまの嘘。
「その古いふるうううい嘘道のなかでも、うちの流派は最古なんだよ」シーノのおどろきをまったく意に介しない、むしろおもしろがっているようすで話をつづける。「その名も百歩七嘘派といってね」
百歩七嘘派。
へんな名前。
「百歩あるくうちに七つの嘘をつくべし、っていう掟があったんだよ発足当時は。違反すればもちろん破門。ま、いまはだいぶゆるくなったから、たんなる心がまえにすぎないけど」
そこまでいうと蛇足軒はまたきゅうにだまった。さきほどとそっくりな症状で卓につっぷし、すこしのあいだそのままでいて、やはりなにごともなかったように顔をあげた。
「じゃあ。百歩七嘘派の歴史について話そうか」
はい、おねがいします。シーノの背中を流れる汗はますますいやな感じになる。
彼は話した。
百歩七嘘派とは。いまから数千年前、南の海に面した都市で勃興した論理数学的哲学集団を起源としている。同時期に栄えた犬儒学派とひじょうに仲が悪く、とくに塔上聖人の是非をめぐっては数百年にわたり泥仕合をつづけていたといわれている。犬儒学派は、塔に登って何十年も祈りながら断食するなど芝居がかった売名行為にすぎない、ほんとうに苦行したいならじぶんたちのように鎖をつけて樽にはいるべきだと主張し、たいする百歩七嘘派はこの聖人が塔のうえでひたすら円周率を計算していることをなじった。かれらは円周率の桁数を伸ばすことより素数表をつくってほしかったらしい。つまり両者の議論はどこまでも平行線で、さいごはおのおのの長が公衆の面前で蛸を食べる競争をして雌雄を決したようだが、どちらが勝ったのかは伝えられていない。
犬儒学派や塔上聖人が実在していたことくらいは歴史に弱いシーノでも知っていた。ならばこの話はほんとうだな、と、うなずきながらやはり神妙にきく。
だが語り終えた蛇足軒はシーノの顔をのぞきこみ、また頬にへこみをつくって笑った。「やった。信じた信じた」
え。まさかこれも嘘。
あごが落ちそうなほど口をあいて面接者をながめる。その間に蛇足軒は履歴書をとりあげ、ひとりごとにじぶんであいづちをうちながら内容を確認した。「うん、いい学校出てるじゃない。うんうん、年齢は二十七歳ね。そっか、ぼくよりちょうど二十、下だ」
ということは。このひと四十七歳。
信じられない。いろんな意味で。
だが相手はシーノの動揺など気にかけるようすはない。「ああ、いいねえ博士号かっこ理学かっことじ取得済」
え。
「とてもいい。ここでの仕事にぴったりな資格だよ」
そんなこといわれたのはじめてだ。
でも、なぜ。
シーノは口だけでなく両目もおおきくひらいて相手をみる。
「だってさ」蛇足軒の目のまわりに笑い皺があらわれた。「理系の博士号もち、ってことは。ある仮説が真実かどうか疑い、検証することを徹底して訓練してきたわけでしょ。そんなひとですらひっかかる嘘を考えつけたら最高だってことじゃない」
うん。まあ、そうかな。
もっともじぶんの専門は理論系でも実験系でもなく希少生物ホラホラ属の分類だけど。
「それとね。そのまったくしゃべらないところ。それも、とてもいい」
こんなこといわれたのもはじめてだ。
たしかに塀の貼紙には書いてあったけど。無口なかた歓迎って。
でも、なぜ。
「きみ理想的だ、うちの秘書として」面接者はふたつめの疑問にこたえないまま履歴書を卓上にもどした。「じゃ、採用。さっそく明日からきてもらえるかな」
ええっ。なんてあっさり。
あまりのきゅうな展開にシーノは驚きっぱなしだったが、それでもしっかりと同意のうなずきを返していた。
翌朝。
指定された時間に蛇足軒をおとずれ、かってに入っていいからね、ときのう別れぎわにわたされた鍵で玄関を開ける。こぢんまりした三和土をあがり、面接につかった居間をのぞくが、たばこ盆をのせた一枚板の長卓のむこうに主のすがたはなかった。
シーノは居間をとっくりとながめた。きのうは室内を観察する余裕はなかったからだ。
部屋は土壁で板張り天井だった。珪藻土かな檜かな、と建築関係のすくない知識をふりしぼって推測する。きのうの印象よりずっとせまい。じぶんの住む貸間よりせまいかもしれない。長卓の両端と壁とのあいだはひとがやっと通れるくらいだ。
左手の壁には掛軸があった。書になど縁のないシーノにもよめるくらいくせのない毛筆文字はこううたっていた。ひとつの嘘より五万回の嘘を。第二十三代蛇足軒、第二百十五代百歩七嘘派免許皆伝。花押。印。
雇い主であるいまの蛇足軒はこの号を名乗る三十三代めで、第二百二十五代めの百歩七嘘派免許皆伝なのだという話はすでにきいていた。これも嘘かと思っていたが、どうやら真実のようだ。
この掛軸が彼の創作物でなければ。
右手の壁に目を移す。つくりつけの書架があって、互いちがいになった三段の棚にあまり新しくはなさそうな本がならんでいた。一歩ちかよって背表紙をよむ。最上段の数冊の本はそろいの装丁で、こんな表題だった。
再発見された嘘いつわりの記録。
その下に番号がついているからつづきものなのだろう。
第一巻を手にとり、奥付をみる。出版は十年以上も前だった。巻末の著者紹介によると、松崎某というこの著者は蛸足大学理学部の出身でシーノの先輩にあたっていた。紹介文はこうつづく。あいつぐ締切により持病が悪化、早世。本作は遺作となっている。なお未完。
かわいそう。
でも、死ぬほど仕事がある状況ってうらやましいかも。
本を棚にもどして目をあげる。部屋の正面はおおきな硝子戸になっていた。その先は縁側で庭に出られるようだ。硝子を通してみえる庭は手入れがゆきとどいており、造園の知識など皆無のシーノにもそのうつくしさが理解できた。隣家との境界である塀にかこまれてせまかったが、子牛ほどもありそうな青い石が置かれそばには松が配され、白い玉砂利が敷かれてちいさいながら池まであった。
さてみとれている場合ではない。雇い主を探さねば。
玄関までもどり、細い廊下を北側にすすむ。たった数歩でおわった廊下の先は台所だった。ひとがふたりも立ったらいっぱいの台所は予想したよりずっとこぎれいだ。たぶん、ろくにつかっていない。日々の食事は店屋物か。
きびすを返して廊下を逆戻りする。居間をすぎると襖があった。外からみたかぎりでは蛇足軒はちいさな平屋だったから、おそらくこれがさいごの部屋だ。ということは、主はここにいるはず。
意を決して襖をひらいた。
せまい居間のさらに半分くらいしかない南向きの居室の床に布団は敷かれていた。だがかんじんの雇い主の姿はなかった。
え。あれ。どういうこと。
室内に踏み入る。かくれる場所などないはずだ、だがみわたせど主はいない。どこだ。どこにいる。
部屋のすみに物入れがあった。引き戸がはんぶん開いていて、裸足の脚が二本のぞいていた。
すねをなんどか強く叩くと蛇足軒は早朝に掘りあげられた人参みたいな声を出した。「ああああ。きたね。シーノさんだっけ」浴衣姿の雇い主は物入れから苦労しいしい這い出てきた。細い体をむりやり折り曲げて入っていたようだ。
シーノのあがった眉をみたらしく、寝癖のついた髪をかきあげながら説明を加える。「あのね、ぼく寝相悪いの」眉がさがってこないのでさらにつけ加える。「ものすごく」
はあ。
寝相が悪いというよりもはや夢遊病の段階ではなかろうか。
「そうそう。きのうは仕事の内容について話してなかったね」彼は両腕をあげておおきなあくびをひとつしてから、浴衣のすそをなおしてシーノを振り返った。「おいで。説明しよう」おっくうそうに立ちあがり、部屋から出ていく。
シーノは子犬みたいに雇い主のあとを追った。
家元秘書の仕事内容、か。
きのう提示された時給は予想よりはるかに高かった。彼女のつつましい生活をじゅうぶん支え、かつ貯金まで可能な額だ。これほどの給与を保証されるのだからむずかしい仕事にちがいない。
じぶんにできるだろうか。正直、事務作業には自信がない。
寝室から居間につづくたった数歩ぶんの廊下を進むあいだに、悪い想像が鉄下駄を履いて脳裏をかけめぐった。長い書類のなかの一字がまちがっているせいですべてつくりなおし。あるいは、帳簿のたった一円が合わないばかりに深夜まで残業。地下室につれていかれ、脚に鎖をつけられる。鎖の先にはお約束のように鉄球がついている。もちろん夜食などあるはずもない。あんどんの明かりだけをたよりに泣きながら無骨な事務用電卓をたたきつづける。しかし、なんどやっても合わないものは合わない。そしてその場所でシーノは、生まれてすぐ引き離され、仮面をつけられて幽閉されていた双子の妹と邂逅する。
もはや事務作業とはなんの関係もなくなったシーノの妄想になど気づくようすもなく、蛇足軒はすたすたと居間に入って硝子戸をあけはなった。「秘書としてのいちばんだいじな仕事はね」外を指し示す。
「あれだよ」
あれ。
池。
それが、なにか。
蛇足軒は縁側に出て、つっかけを履くと庭に降りた。「ちょっと、ここにおいで」飛び石づたいに池の前までいくと、シーノを振り返って手招きする。
またしても子犬みたいに、雇い主のいうとおりにする。
ふたりはならんで池のふちにしゃがみこむ。光のぐあいか不純物のせいか、水は緑色にみえる。その水をとおして、赤く丸いものがゆっくり動いている。
鯉。おおきさからシーノはそう推測する。
「金魚だよ」
えええっ。
シーノが巨大な赤い魚をみつめているあいだ、蛇足軒は早足で家のなかにひっこみ、すぐにまたもどってきた。「毎朝そいつにね、餌をやってほしいんだ。それがなによりもだいじな業務」右手に持った透明樹脂製の小袋を差しだす。
小袋をうけとってつくづくとみた。
たまごぼうろ。
なぜこんなものを、金魚に。
いや、駄菓子ではなく金魚用の餌かも。
だが小袋を裏返して原材料名をみても、砂糖やら馬鈴薯でんぷんやら鶏卵やら牛乳やら、菓子として当然なものしか記されていなかった。これはどこからどうみても菓子だ。
そして。原材料一覧の横にへんな文句が印刷されているのをみつけてしまった。
この菓子は五万個の嘘をきかせて製造しました。
ひょっとしてこれも蛇足軒が袋ごと捏造したのではないか。そう疑う免疫が彼女のなかに形成されつつあった。
採用後数日たつと秘書業務にも慣れてきた。
もちろん事務作業はあったが、予想したよりはるかにやさしかった。雇い主は細かいことを気にしないたちであることも幸いした。しかも、家元なのに弟子の数はきょくたんに少なく、管理すべき予定も金銭の授受もきわめてわずかだから楽なことこのうえない。
では収入はどうしているのか。
書類や郵便物を整理していてわかったのだが、どうやら蛇足軒は市内の一等地や大量の有価証券を保有しているらしい。不労所得がふんだんにあるから、家元としての収入はあってもなくてもかまわないようだ。
道楽か。
縁側から庭に出て、錦鯉とみまがうばかりの巨大な金魚に池のふちから餌を投げながら、ため息をつく。なお、きょうの餌として雇い主から指定されているのは鈴かすてらだった。
家元とは趣味道楽の世界だ。金になるかどうかなど関係ない。その道をきわめればよい、じぶんの気のすむまで。
研究に似てるな。もっとも研究者には給料が出るけど。
緑色の水のなかで金魚がぷかっと泡を吐く。まるくて背びれのない姿をしている。らんちゅう、という品種だ。そのくらいは知っている。
膝をかかえて池のふちに座りこみ、金魚の赤い背中をみつめる。こいつ名前ないのかな。たぶんないだろう。
ここはひとつ、命名してやるか。名前をつけるのは得意だ、分類学においては命名がもっともだいじな作業なのだから。これまで何十種ものホラホラ属に古典語で適切な名前をつけてきた。そうだな、このらんちゅうの名前は。
いちゃぽん。
うん、われながらよい名だ。水面の下の赤い魚をながめながらなんどもうなずく。
蛇足軒にさらなる収入源があることに気づくのはもう数日たってからだ。
シーノが蛇足軒の秘書となってから一週間が経過した。
このころには採用の理由もわかりかけていた。面接時に蛇足軒がみせた失神状態は、長大な嘘を考えるときの癖らしい。彼はしばしばあの状態に陥り、回復すると子犬を呼ぶみたいにシーノを呼ぶ。
いつのまにか彼女は名前を呼び捨てされるようになっていた。
シーノを卓のむかいに座らせ、できたばかりの嘘を語ってきかせる。もちろん嘘だとわかっているのだが、きいているうちにほんとうの話のように思えてくるからふしぎだ。ほとんど信じかけている彼女の表情をみて、蛇足軒は満足そうにじぶんの嘘に採点する。十点満点で八点、ね。そして袂から手帳をとりだし、得点が高かった嘘についてはその内容を評価とともに記録する。
つまり、彼は話の聞き役がほしかったらしい。無口なかた歓迎とは、聞き手がいちいち口をはさまないように、という意図だったのだろう。
ほかの奇行にも慣れてきた。彼の生活態度はでたらめもいいところだった。寝相はきょくたんに悪い。だから彼女の朝は雇い主を探すことからはじまる。寝室にいればまだいいほうで、廊下や台所、はては縁側で寝ていることすらある。それに朝だろうが夕方だろうが、木桶を片手にふらりと銭湯へでかけ、何時間も帰ってこない。まともな食事はしない。口にするのは珈琲とたばこ、そして菓子。もちろんこれらの買い出しもシーノの仕事となっている。
九年かけて博士号までとって、いったいなにをやっているのだ、じぶん。
でも、まあいい。しょせんは腰かけだ、有給の研究職につくまでの。なんたってここ、時給が高いし。
その朝シーノは玄関で花を活けていた。生け花どころか街の花屋で切り花を買うことすら無縁の生活を送ってきたのだが、べつにむずかしいことはしなくていい、枯れてない花が挿してあるだけでいいから、と雇い主がいうのでやってみることにした。たしかにむずかしくない。さいしょに水あげをきちんとする、花瓶の水はまいにち替える、花びらや葉が茶色に変色してきたらまめに除く、などを守ればよいだけだ。
呼び鈴が鳴った。
はさみを置いて振り返り、三和土へ降りて扉を開ける。立っていたのは彼女が知っている、しかし意外な人物だった。
「あれ。シーノさん」職安の若手相談員はふちなしめがねのむこうで目をおおきく見開いた。「ひょっとしてここに就職されたんですか」
うなずくと相手はおめでとうございます、と心底うれしそうに返してきた。「それはよかった。あなたむきの仕事かもしれませんね、これ」
わたしむき。なぜ。
首をかしげる。たしかに当初思っていたより家元の秘書業務はやさしく、たのしいと感じることすらあった。だがじぶんにむいているとまでは思わない。臨時仕事としてたんたんとこなしているだけだ。最終目標は研究職なのだから。
むいてるって、どういうこと。
だが相談員から疑問への答えはない。「心配してたんですよ、さいきん職安に顔をみせてくださらなかったので」でもほんとによかった、ここにきまって。よかったよかった。ところで家元はご在宅でしょうか。
シーノは彼を居間に通した。
職安職員が百歩七嘘派家元などにいったいなんの用事だろう。
硝子戸を開け、庭に出ていた蛇足軒に手招きをする。彼はすぐに気づいて縁側からあがってきた。相談員の顔をみてもまったく驚きもせず、やあやあどうもどうも、といって、長卓についている客のむかいがわに座った。
知り合いのようだ。しかもかなり以前からの。
シーノはますます首をひねりながら台所へいって珈琲の用意をする。こぶりのやかんで湯をわかす。そのあいだに豆を挽く。やかんのふたがかちかちいいだしたら火をとめて、温度をさげるために少量の水を足す。粉を載せる布は袋状で、金魚すくいみたいな金属の輪と取っ手がついている。口の広い硝子容器に布袋をかざし、湯を注ぐ。落ちてくる珈琲は、よくいわれるような悪魔の黒さではない。琥珀色にちかい。果実のようなにおいが鼻をなでる。ふしぎなことに柑橘によく似ている。よい豆はそんな香りがするんだ、と雇い主はいう。
珈琲にせよ花にせよ庭にせよ、要所要所は家元らしく風流だ。
抽出がおわるとふたつの碗に珈琲を注ぎわける。受け皿に載せ、さらに盆に載せて居間へはこぶ。
一枚板の卓をはさんで座った主人と客はすでに話し合いをはじめていた。
「という、特殊求職者なんですよ」卓に碗をならべるシーノに、どうもありがとうございます、と相談員は声をかける。「ところで彼女はだいじょうぶですよね」うかがうように蛇足軒をみる。
その目つき。柔和な若手相談員とはちがう一面をかいまみた気がした。
「もちろん。彼女は筋金入りの訥弁だ、心配ない」雇い主はそうだよねうんうん、といってシーノに微笑をみせる。
彼女はうなずく。そして不安げにふたりを交互にみる。
「懇切、ていねい、秘密厳守。ね」相談員はいつものひとあたりのよい笑顔にもどっていた。「この仕事、守秘義務が重視されるから」
他言無用。
ようやく腑に落ちた。無口なかた歓迎、とはこういう意味でもあったのか。
ではよろしくおねがいします。そういいのこして相談員は帰っていった。
空いた碗をかたづけようとしたシーノを蛇足軒がよびとめ、さきほどまで客がいたところに座らせた。「だいじな話をしようか」
新米秘書が腰を落ち着かせるのを待って、家元は咳払いをひとつする。卓上のたばこ盆に手をのばし、下部の引き出しからきざみたばこをひとつまみとりだす。豆くらいのおおきさにゆるくまるめて、きせるの火皿につめる。「いまの、職安からの依頼の件だ」
彼女は息をのんで雇い主をみつめる。なんだ。なぜ相談員がここにくる。それになんだ、特殊求職者とは。
蛇足軒は燐寸をすり、火皿にちかづけた。点火がうまくいったことを確認したあと浅く吸い、煙を吐いてなんともしあわせそうな表情になった。これを三度くりかえし、火皿に残った灰を竹製の灰入れに落とした。
きせるをたばこ盆に戻してから彼は真顔になった。「職安って、なんの略だか知ってるね」
もちろん。そんなの子供だって知っている。
職業安全保障部局のことだ。
「そろそろ話しとかなきゃいけないかな」
なにを。
「ぼくね。じつは」蛇足軒はいちどたばこ盆に視線を落とし、それからまたシーノをみた。「職業安全保障部局の、特命相談員なんだ」
ええっ。
なんだ、それ。特命相談員って。
そもそも、役人だったんだこのひと。
なんて似合わない。
特殊求職者はさっそく翌朝やってきた。
玄関にあらわれたのはまだ少年といっていいくらいの若い男だった。ひどくやせて目の下がくぼんでいる。顔色も悪い。せわしなく周囲をみまわしてから、引き戸のすきまをすばやく抜けて建物のなかに入ってきた。おびえたねずみみたい、とシーノは思った。きっと猫に追われているんだ。
猫とねずみがはてしない追いかけっこをつづける古い漫画を思い出す。猫はねずみを追う。毎週金曜日には追いつき、ねずみを惨殺する。しかしねずみはすぐ蘇生し、また猫に追いかけられる。つまりねずみは不死身だ。だからこれが毎週、永遠にくりかえされる。この殺したり殺されたりする苦行はかれらに科されたおわりなき罰だ。かれらの前世は人間の男女であり、姦通の罪を犯したのだという。いまにして思えば、子供むけふうのかわいらしい絵柄のわりにとても暗い主題の漫画だった。
蛇足軒が待つ居間へ彼を通して、シーノは台所で珈琲の準備をした。湯気のたつ碗をふたつのせた盆を持って居間に入ると、ふたりは長卓をはさんで差しむかいに座り、話をはじめていた。
「シーノ。きみもここにいなさい」碗をならべて去ろうとすると、蛇足軒がそう声をかける。
いわれたとおり雇い主の横に座る。絶食した喜劇俳優みたいな彼の顔をちらとみあげる。役人。ちっともそれらしくないけど、やはり役人。
特命相談員と特殊求職者の会話はすぐに再開された。
「ほんと、苦労してきたんです。この特異体質のせいで」求職者の青年は視線をななめ下にむけ、細い両腕を体に回していた。珈琲碗に手をつけようともしない。まさに水に落ちてふるえているねずみのようだった。「周囲に知られないようにするのがたいへんでした。でもどんなに気をつかっても、仕事をしていればなにかのひょうしで、ばれてしまうんです」
そうなったらもう、その場所にはいられません。夜逃げ、変名、宿さがし。これまでなんどやったことか。
蛇足軒は彼にしてはめずらしく、珈琲をすすりながらひたすら聞き役に徹している。
話のとちゅうから入ったため、シーノはもどかしい思いをしていた。なんだ、特異体質って。特殊求職者の特殊たるゆえんか。
特命相談員と特殊求職者の顔を交互にみる。だが彼女にたいする説明はない。
「職安に相談しよう、と思いついたのはこの街にきてからです。駅のちかくに建物があって、たまたまみかけて」あの貼紙の標語。懇切、ていねい、秘密厳守、って。
秘密を守ってくれますか。
「もちろん」蛇足軒は碗を置き、微笑を浮かべる。
気をつけろ、このひとは嘘つきだ。シーノは内心で警告する。
それに。そもそもなぜ、嘘道の家元が職安の特命相談員などやっているのか。収入のためとは思えないのだが。
秘書の懸念や疑念には気づかないらしく、特殊求職者は蛇足軒にうなずきを返した。そして立ちあがり、左の袖を上腕がみえるほどまくりあげた。服の奥のほうに手をさしこんでなにかをとりだす。
小刀だった。
え。なに。なにをするの。
シーノがとまどってながめているあいだに、青年は小刀のさやをはずして刃先を左腕の皮膚にあてた。深く息を吸い、止める。ねずみによく似た目が光った。白い刃が肌の上を走る。長い傷ができる。青年の顔がゆがむ。
みたくない。だが、目に入ってしまった。
長卓の上に血が落ちても、青年は冷静だった。痛そうに顔をしかめつつ、持参してきた布を出して流れる血をぬぐっている。
なぜ。なんのためにこんなことを。