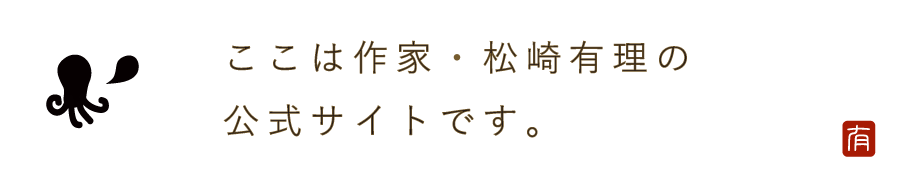作成日:2017/09/19 最終更新日:2017/09/25 かいたひと:松崎有理
出勤前のシーノは、たんすから出したばかりの外套を腕にかけたまま、はい、といって自室の電話の受話器をとった。ききおぼえのある声、いや忘れもしない声が響いてきた。
「シーノくんかい」
そうだ、忘れもしない。忘れるわけがない、この男。
「さいきん研究室に顔みせないけど、どしたの」相手は間延びした口調でいった。「就職活動、順調なのかな」
こいつ、よくもしゃあしゃあと。じぶんの責任を放棄して。
かなりむっとしたが、もちろん口には出さなかった。重度の訥弁だからだ。
「もっとも、まいにち研究室にきたところで就職先がみつかるわけじゃないけどね。あいかわらず研究職の公募は日照り状態だから」大学院時代の指導教官はしゃあしゃあとつづける。シーノはただ、きく。大学院時代とおなじように。
「あいかわらず若いひとたちの進路は絶望的だね」もと指導教官はひとごとみたいな明るい調子でいった。「職安にでも通ったほうがましだと思うよ」からからと笑う。まったくひとごとみたいに。
ものすごくむっとした。そう、ひとごとなんだ。彼のような功成り名を遂げたあとのじじいどもにとっては。
博士号取得後、研究職を探すうえで苦しめられる法律は博士増員十万人計画だけではなかった。やはり十年前に施行された、大学および研究機関における教員定年延長制度。これまで七十歳だった定年を八十五歳まで延長し、優秀な人材が長く安心して活躍できる場を提供する。
現代の男性の平均寿命は八十五・一六歳だから、ほぼ一生大学にいられる目算だ。
いま研究職についている者たちにかぎっていえば。
「それじゃ、たまには大学にも顔を出しなさい。お茶くらい飲もう」御年七十七歳になるもと指導教官はまたからからと笑い、電話を切った。
つうつうと機械音を発しはじめた受話器をにぎって怒りにふるえた。あいつらのせいだ。法律をつくった役人たちと、その法律に乗っかってのうのうと暮らすじじいどものせいなんだ。じじいどもが死ぬまで現職に居座っているから、わたしたち若者はいつまでも就職浪人としてさすらうはめになる。
とっとと引退しろ、じじいども。その席を若者にゆずれ。
大学院時代の記憶がよみがえる。シーノは地下鉄東西線をつかって通学していた。ここ架須賀町通の貸間にほどちかい似詩公園駅から、蛸足大学理学部そばの蒼羽山駅まで、まいにちの往復。
地下鉄のすべての座席は優先席だった。七十歳未満の者、かつみためにあきらかな不具合のない者が座席を使用すれば懲役刑または罰金刑が科せられた。だが若くたって体調をくずすときもあるし、女には月経というやっかいなものもある。三十九度の熱があっても、鎮痛剤も効かないようなひどい腹痛に苦しめられていても、地下鉄で座ることはできなかった。貧乏学生のひと月ぶんの生活費に相当する罰金がおそろしかったからだ。
ああ、超長寿社会。
貸間の低い天井をみあげ、目を閉じる。たしかに近年、平均寿命は飛躍的に延びた。各種健康推進法、たとえば自宅以外での喫煙の全面禁止や、三十歳以上の各種癌検診受診などがきびしい罰則つきで法制化されたのが功を奏したのだろう。だがこのままいけば。
まぶたの裏に近未来の風景が描きだされる。街ゆくひとは年寄り、年寄り、年寄りばかり。若者は目につかない。喫茶店で語らい、立体映画に連れ立ってでかけ、球を撞き酒杯をあげ男女で踊る老人たち。もちろん職場もほぼ老人だ。かれらはいつまでもいつまでも退職しないので新規採用はめったに、ない。若者もすくないのだが求人はもっとはるかにすくないため、倍率は数千倍にもなる。人事担当者もやはり老人で、頭が固く旧弊にしばられているから、この時代になってもまだ紙の、しかも手書きでの応募書類提出を求める。就職へのかすかな希望にむけて、数千枚もの履歴書を自筆で埋め、昔ながらに郵便で送る若者たち。腱鞘炎がかれらの持病だ。写真代や郵送費もばかにならない。しかしそこまで時間と金を投資しても、けっきょく大半の若者は職にあぶれ、困窮することになる。食うや食わずで顔色の悪い若者たちにたいし、老人たちはつやつやした頬でこの世の春を謳歌する。長い長い定年まで職が保障された立場を。
老人天国。
外套を抱きしめて、電話の前の床に膝をついた。じぶんはまだしも幸運だった。いまのところ、じゅうぶんな給金をいただける仕事がある。いまのところ、生活には困らない。貯金だって順調に増えている。
しかし。
あれは、ほんとうにやりたいことではない。ただの腰かけ。そうだ、あきらめちゃいない。じぶんの夢は研究職なんだ。
希少生物ホラホラ属の分類。この専門を活かした仕事がしたい。
立ちあがり、手にした外套をひとふりして皺をのばした。襟の内側についていた洗濯屋の札に気づいて引きちぎる。
外套を羽織って玄関を出る。吐く息はすでに白く、架須賀町通の銀杏並木は黄色い葉を落としつくそうとしている。路面からはつぶれたぎんなんの匂いが立ちのぼる。北の街のみじかい秋は終わりかけていた。きょうもまた、家元秘書としての一日がはじまる。
嘘道、というきみょうな家元の。
るるるるるる。るるるるるるる。るるるるるるる。
嘘道家元のこぢんまりした邸宅、蛇足軒に出勤した直後、廊下で電話が鳴った。シーノは三和土から駆けあがり、球技選手もかくやというみごとな手さばきで受話器をとった。はい。蛇足軒。
二、三度、咳払いがあって、ききおぼえのある声、しかしいまのいままで忘れていた声が響いてきた。「ああ。また、きみだね」
ああ。また、あなたね。
「やつに伝えろ。秘伝書の正統なる継承者はそれがしである、と」男の声は低く、そしてかなりの早口だった。しかし滑舌はよく声量もあるので電話でききとるのに苦労はない。「百歩七嘘派第二百二十五代家元の座はそれがしにも権利があった。やつよりそれがしのほうが家元を名乗るにふさわしいはずなのだ。こんどこそ決着をつける。そして秘伝書を我が手に」
一瞬、間があいた。つぎになにをいうかは容易に予測できた。
「首を洗ってまっていろ」
すっかりおなじみとなった紋切型の台詞の直後、電話は切れた。
はああ、と長く息を吐いて、古式ゆかしい黒電話の受話器を戻した。ここふた月ほど、この名前も顔もわからない男からたびたび電話がかかってくる。内容は毎回おなじ。ほとんどあいづちしか返さないシーノにたいしひとしきりしゃべったあと、いつもの紋切型の台詞をいって、切る。
雇い主に電話のあったことを伝えると、彼はいつも首を振って、ああまたあいつか、とぼやくようにいうだけだ。
いいのだろうか。
しかし事情を知らない新米秘書の立場で意見することはできない。
廊下から無人の居間に入り、障子をあけはなつ。硝子戸のむこうは常緑樹の緑だけを残して冬枯れの色になった庭だ。
もうじき半年だな、ここに通いはじめてから。
めずらしく感傷的なきぶんになって、外套も脱がずに庭をながめていると、呼び鈴が鳴った。
はいはいただいま。外套のすそをなびかせて、いま入ってきたばかりの玄関にむかう。
からり。
内側から鍵をはずしたとたん、引き戸が開いた。なんどもここにきたことがあって、勝手を知っているかのようだった。
男がひとり立っていた。
細身のからだにぴったり合った黒い上下そろいの服をきて、白く長い襟巻きにあごをはんぶん埋めている。肩の下までのばしたまっすぐな髪はみごとな銀色だった。目の下がくぼんでいて高く痩せた鉤鼻だけれど、肌のようすからしてさほど歳ではなさそうだ。雇い主よりずっと若いだろう。四十手前といったところか。
「きみが、秘書さんか」男はシーノをみて数回まばたきし、咳払いをひとつした。「こんなに早くくるとは思ってもみなかっただろう」
電話とおなじ声だった。
「さっき。そこの角で、携帯からかけていたんだ」左手を上衣の奥につっこんで、白く薄い手のひら大の機械をはんぶんのぞかせる。りんごのかたちの企業商標が息をするように点滅していた。
ああ、みせたかっただけね。内心でそうつっこむ。
「やつは」携帯型多機能通信機器をもとどおりしまうと、彼はつづけた。声は緊張ぎみにうわずった。「蛇足軒は、いるか」
まだ寝ております。午前中の来客にたいするいつもの返答をする。
「そうか。それなら」つづきは口ごもってしまって、はっきりきこえなかった。登場したときからずっと背後に回していた右手を、ついに前に出した。
すわ。小刀。いや拳銃。
と、一歩あとずさったシーノの予想はみごとに裏切られた。
銀髪黒服の男が差しだしたのは、籠に盛られたとりどりの果物だった。
シーノはすこしの間、果物籠と男の高い鉤鼻を交互にみつめた。そしてまた内心でつっこんだ。なにこれ。お盆。いや入院。
どういうつもり。首をかしげて訪問者をみる。
「伊太垣で買ってきた」男は有名高級青果店の名前をあげた。しかしそれでは疑問の答えになっていない。
どういうつもり。再度、首をかしげて相手をみつめたが、黒衣の男は果物籠を彼女の両手に押しつけて。
「秘書さん。名前は」ときいた。
反射的に答える。シーノです。
相手は両目の下に皺をつくった。微笑なのだとわかるには数秒を要した。そして彼は。
「じゃ」と、いって片手をあげた。白い手袋をしていることにはじめて気づいた。
ずっしり重い果物籠を抱えたまま、銀髪をなびかせて歩み去る黒衣の訪問者の背中をただながめる。
あれ。家元には会わなくていいんだろうか。
なにしにきたんだろ、あのひと。
それより。いったい、なにものなんだろ。
「なにこれ。お盆か」
シーノは首を振る。
「じゃ、入院見舞い」
またも首を振る。
「それにしても高そうな代物だなあ」昼ちょっと前、その日の寝床としていた空の浴槽から這い出てくると、蛇足軒は居間の床の間でめざとくあの果物籠をみつけた。長卓に移動させ、さっそく飾りやら透明の包装やらを取り去る。「うわあ、これなんてでっかいぞ」と、持ちあげたのは朱色がかった橙色のみごとな回転楕円体だ。果物にさしてくわしくないシーノだが、南の地域でのみ収穫できる希少品で、まことに値の張るものだということくらいは知っていた。
シーノは長卓の差しむかいに座り、かるく首をかしげていた。頭のなかではさきほど浮かんだみっつの疑問が互いのしっぽを追いかけ合ってぐるぐる回っている。家元には会わないのか。なにしにきた。そもそも、なにものなのか。
蛇足軒は籠の中身をひとつひとつ取りあげては卓上に並べていたが。
「あれっ」底のほうから紙片をいちまい抜きだした。広げて視線を走らせ、なんともしぶい顔をする。
シーノが身を乗り出すと、相手は紙片の皺をのばし、彼女の目の前に置いた。
こんなことが書かれていた。
秘伝書かならずいただきに参上したく候 黒耀斎
「あいつの号だよ」蛇足軒はよりいっそうしぶい顔をして、卓上のたばこ盆をひきよせた。
号、ねえ。ちょっとかっこいいかも、だれかの号とちがって。
だが再度、その号をみつめて考え直した。やっぱりこれ気負いすぎだな。かっこいい、を通りこして向こう側へいっちゃってる。
だれかの号は気を抜きすぎだけど。
きせるに刻みたばこを詰めている雇い主を半眼でみながら、そんな感想を抱く。
家元は燐寸で火皿のたばこに点火して、まず一服してから、ひきつづきしぶい顔でこういった。「それ。裏もあるんだ」
どれどれ。紙片をひっくりかえす。
おなじ筆跡でこうあった。
ひと知れぬおもひのみこそわびしけれわがなげきをばわれのみぞ知る
えっなにこれ。古語。ええと、歌。
古典教養の欠け落ちた真性理系脳が答えを求めて右往左往しているあいだに、蛇足軒は三服吸い終えて、きせるの灰を竹製の灰入れに落とした。「まったく、まわりくどい。しかもこれ剽窃じゃないか」
まあ、あいつらしいけどな。そういう蛇足軒の顔は、だいすきなたばこを吸った直後にもかかわらずしぶい表情をたもったままだった。
なんだろ。
さきほどの疑問たちはさらに回転速度をあげてシーノの脳内をかけめぐる。なんだろ、なんだろ。
質問してみようか。